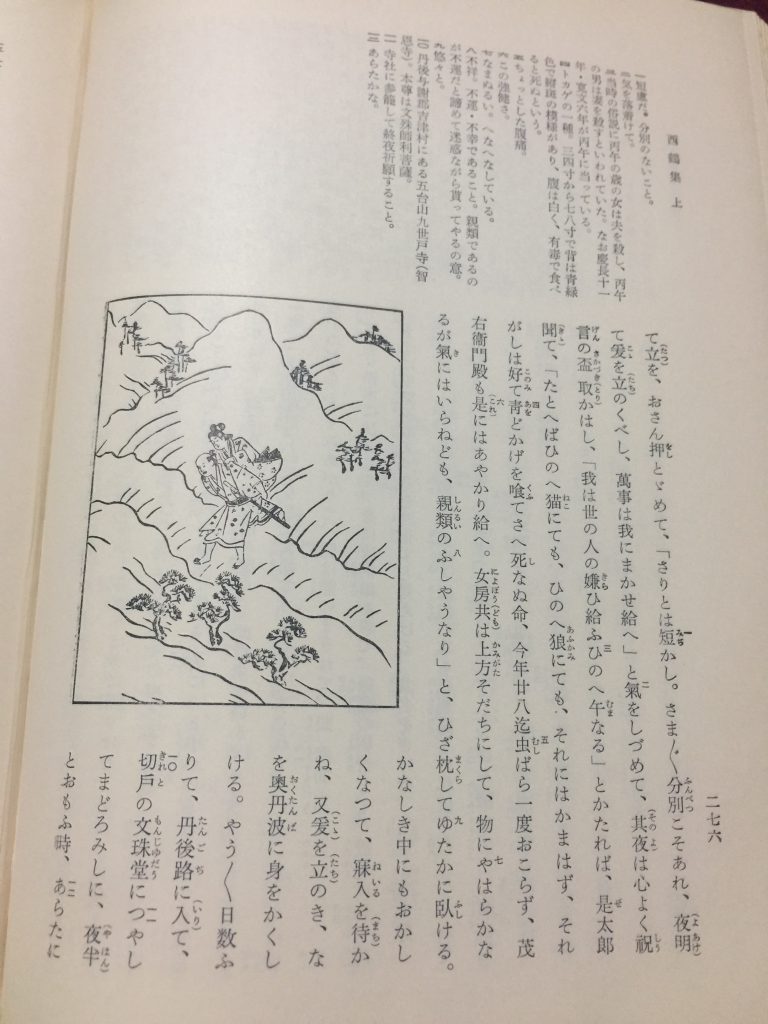井原西鶴-「好色五人女 巻三」1686
溝口健二監督の映画「近松物語」に強く心動かされ、その原作である近松門左衛門の人形浄瑠璃「大経師昔暦」を読んだ感想を先に書いた。しかし思うところをうまく書き言葉にできないところが多かった。さらに、同じ実際の事件を題材とした井原西鶴の手による小説も読まねばと思うに至った。
西鶴版は「好色五人女」の巻三「中段による暦屋物語」である。
きちんと西鶴を読んだのは初めてだった。何よりはじめの印象は、なんてきれいな文章だろうということだ。物語は好まないが、太宰治のその文章は本当にきれいだ。言葉遣いにリズムが流れるようである。その他、名文と呼ばれるその他の作家の文章に触れても、太宰の文章ほどまさに流麗で爽快なものをまだ知らない。西鶴の文章は太宰の文章を思い出させた。近松の文章も美しいと感嘆したが、やはりそもそもが「語る」ための太夫の台本であり、読み上げの音と韻律の美だ。近松は「読む」文章としての美しさだ。言葉それ自体の美しさとその表現用法のつなぎ方や響きの韻律が絶妙。全体がうまくまとまり、簡素で明解だ。やはり詩心は文章に生きるということを改めて思う。
岩波日本古典文学大系の西鶴集上巻に収録なのだが、長さは20頁ほどだ。短い。全五段の冒頭は、ひたすら京の遊び人が通り過ぎる女性たちを品定めする段だ。その遊び人の紹介はこうだ。
「折ふし洛中に隠れなき騒ぎ仲間の男四天王、風義人にすぐれて目立ち、親ゆずりの有るにまかせ、元日より大晦日迄、一日も色にあそばぬ事なし」
多額の遺産で毎日遊び歩いている評判のイケメンというわけだ。その遊び方について続けて述べているのだが「衆道女道を昼夜のわかちもなく」とある。衆道とはもちろん男性同士の性愛のことで、両性愛者であることがさらりと書いてある。当時は少年男娼を並べた遊郭があったほど男色が公認の性文化として社会にしっかりと馴染み人々の性意識に浸透していたと知識で知ってはいても、こうした「時代による価値観の相違」を見ると、今私たちが「当たり前」と感じている「常識」や「印象」も所詮相対的なものにすぎず、すこぶる危うい頼りないものなのだと改めて教えてくれる。或る事象に対して抱く感情や感想を当たり前と疑わない態度の愚かしさを思う。
そして行き交う女性たちに対する品定めの文章だが、10代から30代までそれぞれの女性に対し衣装、振る舞い、容貌などあけっぴろげで不躾なまさに品評の言葉が並ぶ。特に容貌については執拗というかその執心ぶりがにじみ出る。たとえば34、5歳の或る女性についてはこうある。「首筋立ちのび、目の張りりんとして、額の生え際自然と麗しく、鼻思うには少し高けれども、それも堪忍ごろなり」またこれは15、6歳の娘に対する品定めの文章だが「顔は丸くして見よく、目に利発あらわれ、耳の付きようしおらしく、手足の指豊かに、皮薄に色白く、衣類の着こなしまた有るべからず」顔型や目はともかく、耳や手足の指まで執拗な品評眼でそれこそ舐めるように見つめ、それを描いている。つまり、対象から受けたこちらの「印象」をただ観念として羅列するのでなく、できるだけ対象をそのままに読者に提示しようとするリアリズムだし、その生々しさは対象偏愛のフェティシズムにも近接している印象だ。
ところでこの部分ほとんどは本編の物語とは関係がない。おさんの美貌を最後に強調するための前振りでしかない。不自然な長さ。もしかしたら、このあたりの文章は読者への「サービスシーン」なのかもしれない。これは取り澄ました芸術作でなく、あくまでも大衆向け読み物である。
ここからが物語。問題の、密通のいきさつについてだ。まず手代(茂右衛門)に恋している腰元りんがいる。しかしりんは文字が書けず手紙を書いて手代に打ち明けることができない。それを知ったお内儀のおさん。ちょっとしたいたずら心もあって、りんに成り代わって手代へ恋文を書く。はじめはまともに取り合わない手代だが、なんとも情熱的な手紙をいくども貰ううちに、手代もりんへの恋心を募らせる。その手紙だが、内容は露骨で契り重ねたらやがて妊娠するなど挑発して気を引いているのだ。なんとも罪作り。書き手が実はおさんだとも知らず騙されている手代からの返事を読んでは女房たちと大声上げて笑っているおさんなのである。さらに悪のりして、おさんはいよいよ日を指定してりんの寝屋に忍び込んでほしいと茂右衛門を誘う。そしてりんの粗末な寝着に身を包み、おさんがりんの代わりに布団に入り隠れて待つのだ。茂右衛門が訪れたら大声上げて、それを合図に女房たちが駆けつけて恥をかかせる算段である。わざわざ撃退するための打ち棒まで用意している。ところがおさん、昼間にはしゃぎすぎたせいで爆睡してしまう。深夜、忍んでやってくる茂右衛門。相手をりんと疑わず、思いを果たすのである。そのあとで目を覚ましたおさんの狼狽ぶりが描かれる。「その後、おさんはおのずから夢覚めて、驚かれしかば、枕はずれてしどけなく、帯はほどけて手元になく、鼻紙のわけもなきことに心恥ずかしく」何しろ、密通は死罪である。愕然として「このうえは身を捨て、命限りに名を立て、茂右衛門と死出の旅路の道づれ」と腹をくくる。茂右衛門もはじめはりんと思っていたが、今やおさんに心奪われ夜ごと通い情を重ねる。そして逃避行である。
これをまず現在からの観点で点検する。おさんが熟睡している最中に行為を遂げたのであれば、これはれっきとした(準)強姦である。つまり互いの「合意」が前提となっていない行為なのだから、たとえ恋仲だと抗弁しても無駄だ。そもそもおさんは茂右衛門を笑いものにしようとしたのであり、セックスしようという意図などなかった(とされている)。ここで結果責任として「不義密通」を犯したとして夫人を処罰するのは、今でも時折国際的なニュースとなる「名誉殺人」や「レイプ被害者への刑罰」につながる価値観だ。女性(妻、娘)を男性(夫、父)の所有物とする差別観とみてよいと思う。
しかし、当時はこれが「可哀想」ではあっても、「倫理」であったわけだ。「正しかった」のである。
そしてここにもう一つの要素として、「夜這い文化」の問題がある。
茂右衛門はりんの誘いに応じてりんの寝屋に忍びこみ思いを遂げる。こう書かれてある。「茂右衛門下帯をときかけ、暗がりに忍び、夜着の下に焦がれて、裸身(はだかみ)を差し込み、心急くままに言葉交わしけるまでもなく、よきことをしすまして、袖の移り香しおらしやと」
美しくそのものの描写であるが、相手の意志や同意の有無はもちろん、そもそも起きているのかどうかさえ茂右衛門は問題なしとして行為に及んでいる。そしてこれは一方的な無理強いでなく、恋文を交わし合い高ぶった恋人同士の最初の性交渉なのである。交際を楽しむ例えば「デート」のような中間媒介がなかったのであるから、そのままいきなりが性交渉になるわけだが、なんとも直截的すぎる。言わば、セックス行為がデートなのである。それも互いの感情的な交流を肉体的快楽に重ねることもなくひどく直線的で単純な行為そのものに見える。
こうして互いにまったく意図せず肉体関係を持ったことで、禁忌によるつり橋効果もあっただろうが、二人の恋情はここより燃え上がることになる。つまり恋情より先に行為があり、行為があってから恋情が生まれている。これは現代の一般的な恋愛観、性意識ではいくらか違和感を覚えるところだ。
溝口健二による映画ではここを逆転させ、はじめの出会いを思いがけない鉢合わせにとどめて行為を後回しにしている。そしてはじめから手代はおさんに恋情を抱いていたと設定しなおしている。つまり、恋情が先にあり、その成就としての性行為という現代の恋愛観、性意識に合わせたパタンに変更しているのである。
おそらく江戸中期の庶民には溝口映画設定の展開ではリアリティも興奮も呼ばなかっただろうし、現代人には思いがけず意図せぬ相手と性交渉してからの恋情の高まりなど共感してはもらえないだろう。
これは日本社会に連綿と続いていた「夜這い文化」の消滅が大きく影響していると見て間違いないだろうと思う。
寝ている女性の寝屋に深夜密かに男性が忍び込んで関係を結ぶ夜這いという風習においては、相手を取り違えることなどざらにあったであろうし、狙う相手を明確に特定せず曖昧なまま向かい、また迎えることもあったのではないか。
特に日本の夜這い文化に精通している訳ではないが、宮本常一のフィールドワーク「忘れられた日本人」で昭和二十年代頃まで実際に残っていた地方の夜這い文化が詳しく記録されている。それは村落の青年男女の公認された通過儀礼であり、また祭りという非日常のハレに設定されたフリーセックスという人気イベントである。宮本の調査では、そのための小屋で男を待つ娘は拒否権を有している。訪れる男は自由だが、娘の方も相手次第で拒むことが出来る。そしてそうした若者同士の交歓を重ねる中で、互いに相手を一人に定めて一対の夫婦が誕生するという。つまり、ここでは性行為に先立つ恋愛は必ずしも必要でない。行為のあとから恋愛が始まるのである。つまり、西鶴が物語に描いた通りそのままである。
行為か恋情、どちらが先というのでなく、それは二つで一つのものだったのではないか。つまり、恋愛と性を別物として区分けし、恋愛を独立したロマンチックな感情として日本人が意識し始めたのは歴史上は最近のことに過ぎないのかもしれない。
ただ中世貴族文化における男女の恋情と行為についてはまた全く別物との印象を持つ。女性の姿を見ることも声を聞くこともなく、言わばただその噂を聞いただけでその女性の虜となり、寝られぬほどに執着し、なんとしても行為を果たそうとあの手この手を尽くす。これはまたリアルには理解しがたい。この時代については私自身が無知すぎる。
それはともかく、ここでも「時代による価値観」の変異が明らかに見て取れる。現代が、恋愛を性と切り離して優美なものとしたために、性は卑しく穢れた隠すべき秘め事になったのかもしれない。どちらの時代の価値観が優れているのか、それは検証不能である。できるのは現代の価値観で眺めるか、あるいは当時の時代における空気や価値観を努めて学びその尺度で以って当時の人と同じように作品を味わうことだろう。
当時の味わい方をできてはじめて、現代に通用する翻案が可能になる気がする。それが過去の名著の脚色の醍醐味だろう。