「割木を書く」(中川一之 『文芸たまゆら』129号)
人間は自分に都合のよいナラティブによって自分を保っている。それは非難されるべきことでもない。 だから一人称の語りはあてにならないことを逆手にとって、信頼できない語り手と暗黙に示すことで、作者は書くことによってでなしに、書かないことによっても...
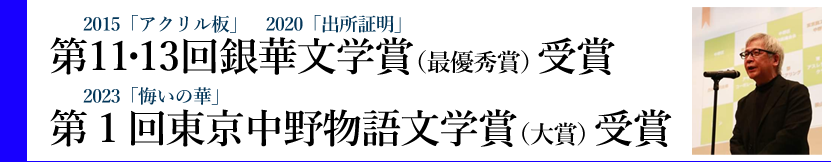  |
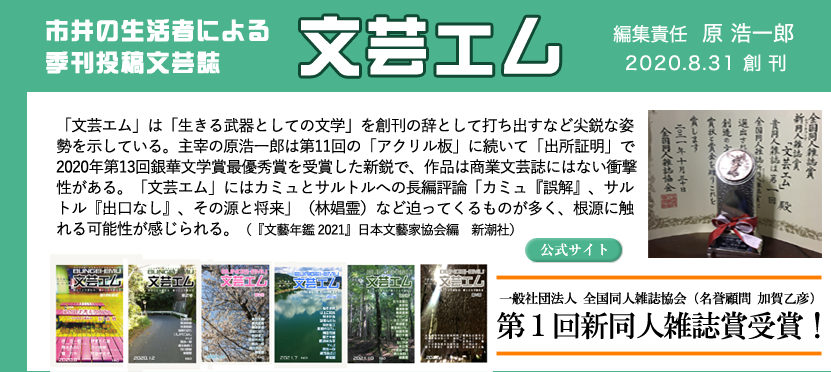 |
| |||||||||||||||||||||
人間は自分に都合のよいナラティブによって自分を保っている。それは非難されるべきことでもない。 だから一人称の語りはあてにならないことを逆手にとって、信頼できない語り手と暗黙に示すことで、作者は書くことによってでなしに、書かないことによっても...
前回はその頃注目されていた教皇選挙にまつわる様々な映画、建築、絵画、その展覧会など話題を自在に転じ、さらにはトランプの教皇コスプレAI画像であるとか、話は連綿とコラージュ的につなげられ、最後選挙の会場であるシスティナ礼拝堂のミケランジェロに...
本当にそうなのか。 文学は深いところで問いかける。 「これはこう」「そうに決まっている」 そうした「当たり前」「当然」の認識や湧きおこる情動について、読む者が深いところで疑問を宿す。 たとえば、苦しむより喜ぶ方がいいに決まっている、争うより...
昨年の熊野大学で初めて浅田彰氏の講演を聞いた。後に「新潮」で特集された記事のレポートでは触れられていなかったが、参加者に向かって挑み煽るように「男であるということが恥ずかしくないのか」という意味の言葉が二度にわたって強い口調で発せられた。深...
「季刊文科」最新99号の同人雑誌季評に、私が「WORKS1」に書いた「雲の火ばなが降りそそぐ」が取り上げられている。冒頭9頁に渡る評者河中郁男氏の論評は読むからに力がこもり、熱を帯びている。前半は主に三里塚闘争とはなんであったのか、という問...
神戸新聞(2025/4/23付)の文芸同人雑誌評に『WORKS1』掲載の「ペトリコール」が取り上げられた。鮎京慈仁の作品だ。うれしい。 これまで『WORKS』からは「サラ・ジェーン」(桑島明大)が『週刊図書新聞』に、そして「影炎ナイフ」(陸...
「それがネガティブ・ケイパビリティ、短気に事実や理由を求めることなく、不確かさや、不可解なことや、疑惑ある状態の中に人が留まることが出来る時に見出されるもの」 (J・キーツ 弟宛書簡から) 中上健次による脚本の映画「火まつり」を観た。ラス...
「歳をとることは人生を語らないことの言い訳にはならないぜ」 たしかにさらに若い方と比すればたとえ20代であっても自分は年寄りだと思うのかもしれない。しかし正真正銘の年寄りがこの言葉を前に奇妙な当惑を覚えるのは何故だろう。 人生を語る老人ほど...
すっかりブログを書かなくなった。このブログ最後に記事を書き込んでからもう10か月がたっている。以前は勝手気まま、頻繁に書き込んでいたのにだ。理由ははっきりしている。このブログを読むであろう人たちがあらわれたからだ。 以前はおそらく誰の目にも...
ずっと気になっていることがある。発端は江藤淳の「成熟と喪失 ”母”の崩壊」だ。その副題が示す通り、当時第三の新人と呼ばれた安岡章太郎や小島信夫らの作品を読み解き、「母」が崩壊し喪失することによって果たされる戦後社会...
全国同人雑誌協会の第一回全国同人誌優秀賞を私が主宰する「文芸エム」が受賞したと連絡があった。さらに新人賞の候補となり8月に選考会が行われるのだという。喜んでいた矢先、「文藝年鑑2021版」の冒頭同人雑誌の項に「文芸エム」とその主宰者として...
京阪丸太町駅の地下ホームだったと思う。裁判所を退職して一年もたっていなかったから、当時勤めていた弁護士事務所からの帰りだったのではないか。 電車を待ち、ホームに立っていたときだ。私は胸の奥がきりきりするような寂しさを感じていた。それは「...
恥ってなんだろう。 先週、自転車で琵琶湖を一周した。朝6時に家を出て、湖岸をぐるり200キロだ。帰宅したのは夜8時過ぎ。途中前夜にこしらえた弁当を食べながら一時間休んだから、13時間走り続けたことになる。もちろん所々で喉を潤したり、コン...
そのころ私は弁護士事務所の事務員だった。今も界隈の雰囲気はさほど変わっていないのではないか。裁判所の近隣はいたるところ弁護士事務所の看板だらけであった。「京都市中京区丸太町麩屋町通り下ル」これが事務所のあたりの住所だ。私は9年間在籍した家...
ある中学生の少女がおびえた様子でお母さんの布団にもぐりこんだ。「変な男が女の子を殺す話を読んだ。怖い」と言うのだ。その小説は「納屋を焼く」。村上春樹の有名な短編だ。 加藤典洋「創作は進歩するのか」というブックレットにそのエピソードが語ら...
三田誠広「野辺送りの唄」を読んだ。 ずっと読みたいと思っていた。実はストーリーも物語のトーンもすっかり忘れ果ててしまっているが、40年前の発刊直後に私はすでに一度読んでいる。そのとき私は衝撃的な深い感銘を受けている。すっかりファンとなり...
「亜細亜二千年紀 第一部亜熱帯へ」を読んだ。 五十嵐勉氏による大長編小説の冒頭部分だ。その構想については折々氏が語られていたが、直接その執筆について話を聞いたのは昨秋である。時代と地域民族を超えてつながる争乱の大叙事詩。私はそう理解した。も...
ゴーゴリ「外套」を読んだ。これまでゴーゴリを読んだことはなかった。ゴーゴリだけではない。実はプーシキンもチェーホフも読んでいない。ロシア作家ならほぼドストエフスキーとトルストイしか読んでいないと言った方がいいかもしれない。ロシアに限らない...
甲南高校文学部、そう口にすると関西では大概勘違いされ、戸惑いを与える。関西には「ええとこの子」が集まる「金持ち大学」甲南大学があるからだ。甲南高校と言えばその高等部だ。しかし文学部であれば、甲南大学だろうと話は混乱する。おまけに私がもとより...
読み終えた。 はじめに岩波文庫「白痴」上巻を開いたのは、いよいよコロナ禍非常事態が宣言され、学校やほとんどの店舗、会社がシャッターを下ろし、まもなく町中からティッシュやマスクが消える頃だ。ひと頃はほぼ毎日、私は「白痴」を読みながら川沿い...
書くとは、言葉に託し内なる形なきものを外に表す営みだ。つまり、まずそれは自分の内に潜むものを自分自身の眼前に突きつけることになる。書くことが、自分自身との思いがけない邂逅をもたらすことを作家や詩人は否応なく自覚している。 その邂逅は至上...
人生の岐路で胎にずんと来る小説と出会った人は多い。たとえば、それまでならば当てにし頼りにしていた人の言葉が、どうしてなのかまったく心に届いてこない。気がついたらどこにも明かりや支えが見当たらない。そんなとき、何気なく手にした文庫を開き、綴...
今年の開催中止を受け、来年3月21日に次回前橋文学フリマが開催されるとメールが届いた。しかし残念ながら、来春にコロナ禍が収束している保証などない。むしろその後は「復旧」でなく「創出」を迫られる不可逆的な歴史的変容を私たちは今体験している。...
吉行淳之介の選による「純愛小説名作選」と銘打たれたオムニバス短編集である。発行は1979年。13編のうち10編を読んだが、とても面白かった。巻末に吉行と長部日出雄による「純愛とは何か」と題する対談が掲載されてあるのだが、出だしから「純愛の...
やはりと言うべきか、前橋文学フリマ中止の連絡が昨夜届いた。開催の約十日前の決定である。すでに納めている出店料は費用を差し引き、その半額を返金すると記されていた。今の若い文学ファンはおしなべて大人しいので、落胆しても黙って事態を受け入れてゆ...
金子光晴の自叙伝「詩人」に少しだけ萩原恭次郎の名が出てくる。金子が「こがね蟲」によって新鋭の耽美派叙情詩人として登場した大正末期の頃のことだ。ちょうど同じ年にアナキズム系詩誌「赤と黒」が萩原恭次郎らによって創刊されている。その創刊号の表紙に...
次回の文学フリマの開催地は前橋である。実ははじめ出店参加するつもりはなかった。私の住む関西からかなり遠いという漠然とした印象があり、なじみを感じなかったのが理由のひとつだ。しかし文芸思潮の五十嵐編集長から前橋でもコラボ出店しましょうと誘われ...
どうしても感想が書けない。 「プリズンサークル」観て一週間がたつ。 そうなんだけど、そうなんだけど、と思いが込み上げるが、言葉が止まってしまう。 数年前、京都刑務所に移転問題が起こった。 先日四選を果たした市長が選挙公約に刑務所移転を一行加...
国土を支配した急進過激勢力による人民大虐殺を逃れ、ようやく国境にたどり着くも隣国から入国を阻まれ、やむなくそこに民衆の難民集落、キャンプ村が出現する。虐殺と飢え、強いられる密告と強制労働による筆舌尽くしがたい過酷の日々から逃れ、そこには束の...
冒頭、有閑貴族紳士たちが延々繰り広げる冗長で衒学的な議論は、当時の典型的な思想の一片が明瞭に語られており興味深くはあったが、(作家の意図通り)退屈に思われた。しかし、森番メラーズが現れてからは、ぐいぐいと物語に引き込まれ、文庫560頁だから...
前に内田樹の「寝ながら学べる構造主義」を読んで頭の中がひっくり返るくらい衝撃を受けた。私を知らず支えていた巨大な柱が見事に倒壊してしまった、という感じ。まったく自覚はなかったが、私は実存主義の子であり、それは他の同時代人も一緒である。主体性...
彼の途轍もない表現の力をなんと言い表せばよいだろう。遠くからでもわかる美しい顔立ちや均整の取れたしなやかな体躯の見栄えまでが加担して、溢れかえるほど魅力が噴出して比類のない表現の巨大な源泉となっている。 私は叫ぶ演技はあまり好きではない。い...
はじめて「こころ」を読んだ。ようやく。実は読みながらずいぶんとツッコミ入れていた。 ともかく気になったのは先生の奥さんについてだ。その描き方がどう見ても大人の女性というより、少女のようだし、これは男の好むひとつの幻想としての女性像に思われ、...
とても晴れ上がった青空だ。いつも朝早く出発せねば間に合わないのだが、今回は近場だ。余裕をもって朝十時に会場に到着した。 これで出店は四回目となる。開場前の準備も随分と慣れた。ブースの狭いスペースにうまいこと作品を陳列する。 今回は何しろ「文...
昨日の文学フリマ京都で信じられないような出会いがあった。私のブースの前で一人の男性が興味深げに私の作品を手に取っている。声をかけると、なんと30年前に私が使っていた筆名を口にされた。あまりの驚きに、すぐに返答できなかった。 実は30年前に一...
青春18切符が一回分残っていた。今季の使用期限は1月の10日である。もともと金券ショップで3回分を購入したものなので、残り1回分を売ってもよかった。購入したときに買取金額100円追加のクーポンも貰っていた。しかし惜しい。またゆっくりJR乗り...
いよいよ1/19に岡崎みやこめっせで第四回文学フリマ京都が開催される。ところで「みやこめっせ」ってまだ馴染めない。勧業館といった方がピンとくる。これは大山のぶ代のドラえもんでないと十年経っても依然違和感覚えるのと同じでどうしようもない。 ...
2019.11.24 東京文学フリマレポート 「文学フリマに魅せられて」 原 浩一郎 会場に到着して驚いた。一般来場者が長蛇の列なのだ。まだ開場まで一時間以上もあるというのに。 東京の文学フリマは大規模だと承知していたが、目の当たりにし...
私がかなり以前に格闘家の船木誠勝氏に送った質問に対して、年頭の動画で30分に渡り語っていただきました。生きるという闘い、死を覚悟すること、そして生き伸びること。 ▼私の質問 「以前の動画で重病患っておられる方へのエールとして『何かと闘ってお...
消防士たちを描いた素晴らしい劇を観た。まだ上演中なので物語の中身まで書くわけにはいかないが、Teamクースーによる第6回公演「分署物語」だ。 脚本演出を手がけた古屋治男氏はもともと消防士だったという。だからリアルな男の職場のあるあるエピソー...
ベケットを観た。舞台ではない。没後30年映画祭で「ゴドーを待ちながら」が上映されたのだ。ベケットの戯曲をフィルム化しようというプロジェクトによるものらしく、戯曲を丁寧に映像化したものだという。 実はベケットについてまったく知らなかった。事前...
フェリーニの「道」を見た。何回目だろう。それでも見るたび新しく映りまた深く味わえるというのは大した作品だ。 今回気がついたのはこの作品もまた何が正しく、何が間違っているか、何が良いことであり、何が悪いことなのか、示してはいないということだ。...
今日は12月8日、真珠湾攻撃、そしてジョンが暗殺された日。 昨日生の演奏を味わったせいで、なおさらジョンのこと思う。もう12月になれば町に山下達郎のクリスマスイブが流れ出す頃もあったが、時代はもうさらに暗くなっている。ジョンのHappy...
嵯峨嵐山と言えば京都を代表する観光の名所とされる。渡月橋から嵐山竹林界隈、日中は大変な人並みで中国語が声高に飛び交っている。 JRの駅を降りるともう辺りは暗かった。目指す場所は老舗高級料亭たん熊北店、熊彦である。この歳になってもマクドやネカ...
敗者が背負う悲劇性については言うまでもないが、勝利が正当性を証明することにはならないように、敗北もまた被害者として正当性を自動的に付与されるわけではない。 敗者が勝者の非道を暴く執念にとり憑かれるのは、勝者は常にその勝利故の権力を以って不正...
他のシェイクスピア悲劇の戯曲と同様、「マクベス」の読後にも不可思議な評価不能の無音状態に心が停止した。 これまでどおり発酵するまで少し時間を置いたらよかったのだが、古書店の店先で開いた文庫本の冒頭にこんな一節を見つけてしまった。 「『ハムレ...
2019.10.19「第三回全国同人雑誌会議」@お茶の水 池坊会館 なぜいま同人雑誌か 第3回全国会議に向けて 五十嵐勉 流されず、考える力を 広がる電子媒体 活字文化が危機に瀕している。深刻化する出版不況に加え、週刊誌・月刊誌の売...
● 沈既済「枕中記」 中国故事に言う「邯鄲(かんたん)の夢」の元になった物語と知らずに読んだ。だから最後の種明かしにすっかり驚いた。「邯鄲の夢」とはいわゆる「夢オチ」のことである。しかし、知らずに読めば「枕中記」物語に「夢オチ」を予感させる...
とてもとても面白かった。ずっと思っていたことが脳科学的に裏付けられた思いがする。断っておくが、私の読み方については先に少し説明が必要だ。私にとっては自明でも、人から見たらそうでもないらしい。私は、たとえば脳内物質の分泌や伝達物質の作用と心の...
読んだあと、すぐにでもその印象や連想を素材にして考察を書ける作品もあれば、なんともひっかかりがなくネタにできないものもある。それはもちろん作品のせいというよりも、私の側の勝手な変数が導いた値にすぎないが。 「ハムレット」を読んだ。先に読んだ...
週末お茶の水で「第三回全国同人雑誌会議」が開催される。参加の予定である。 私は文芸同人誌に所属はしていないが主催の文芸思潮から案内があり、ちょうど同人グループを立ち上げたいと考えていたところなので参加することにした。 基調講演は三田誠広であ...
リア王の王権譲渡をめぐる約ひと月の騒動の間に関係者のうちほとんどが非業の死を遂げ、生き残るのはほんのわずかだ。この凄まじい急転直下の崩壊はどういうことか。 冒頭リア王は、旺盛な我が権力を生前に譲渡するため国土の分割を自身への賛美の度合いで決...
どうしても気になり、ソポクレス自身の「アンティゴネー」の戯曲台本を読んでみたくなった。長く借りていた本を抱え県立図書館へ向かったが、長期延滞の小言をもらうだけで図書を借りることはできなかった。やむなく、BookOffまで出かけ、呉茂一訳の岩...
狭義の三部作とは言えないらしいが、ギリシャ神話のオイディプス(エディプス)を題材としたギリシャ三大悲劇詩人ソポクレスによる戯曲三作品「オイディプス」「コローノスのオイディプス」そして「アンティゴネー」である。 よく知られるオイディプス王自身...
先日、ふと尾崎豊の「I love you」を外国人Youtuberが聞くReaction動画を見た。尾崎については、若くして死んだ日本で有名なシンガーソングライターという程度の予備知識のようだ。もちろん歌詞はわからない。みるみるそのYout...
「唐代伝奇」を読むと、「異なもの」に対する深い畏敬と親和がうかがわれる。妖狐、龍、魂、白猿等々、それらを妻と迎え、あるいはその子を産み、災いどころか思いもよらぬ幸福を手にする。これは逆に信じがたい好転の結果を前にして、後付けで超自然的な力の...
悲劇、つまりその物語が喜びや楽しさよりも悲しみを描くもの。希望や安堵を最後に与えるのでなく、「救いのない」物語。それが古くから演じられ描かれてきたのはなぜなのか。その理由ははっきりとわかる。この世界が、人が生きるということが、決して最後に救...
イベント開催の間もずっと考えていたのは、ここに集まった人たちにとっての「書く」という行為の意味合いについてだ。来場者ではない。出店者についてだ。なぜ書くのだろう。まるで他人事のようだが、それは私が書く「理由」についても明らかにしてくれるよう...
先日、或る芥川賞作家が選考委員となっている比較的小さな文学賞に応募し、受賞は果たせなかったが最終選考に残ることができた。相変わらず書いては応募を続けているのだが、このところ早々に返り討ちに遭うことが続いていた。応募三〇〇人レベルだとトップ...
もちろん文学は道徳や倫理すらも俎上に載せる地平から立ち昇るものだ。だから本来タブーもない。文学はそれゆえに私たちの日常を見えないまま支配している「前提」を対象化させその安寧を突き動かす。前提による安心に執着する精神にとって、それは不快であ...
昨日、龍谷大学犯罪学研究センターが共催するイベントに参加した。高校生中心による薬物事犯の模擬裁判だ。 構成はセンターによるので、もちろん実際の裁判の運用に基づいている。設定もしっかり工夫されている。否認事件のため証人尋問が重ねられ、即日の言...
今年もまた去年のように猛暑が続くとはつい先日まで想像もされなかった。七月下旬になっても鬱々と雨が降り続いていた。ようやく一日曇り空が持ちこたえてくれそうに思われた25日、自転車で琵琶湖一周に向かった。いわゆる「ビワイチ」である。 なんとか「...
念願していた安田登さんの講座をお聞きすることができた。大阪山本能楽堂の伝統芸能塾まっちゃまちサロンだ。時間も短く、また入門講座なので深淵なテーマもさらりと語られるにとどまったが、いくつかとても感じ入る話があった。 能の主人公に当たるシテに対...
ロシアを舞台とした映画をたて続けに見た。「ドクトルジバゴ」「レッズ」、そして「ひまわり」。 「ドクトルジバゴ」はパステルナークの小説の映画化である。見たいと思いながら一度も機会がなかった作品だ。敬遠した理由のひとつには上映時間が3時間を超え...
僕は格闘技が好きだ。しかし格闘技どころか、体育以外スポーツの経験もほとんどない。学校の部活も美術に文芸だ。だからコンプレックスの裏返しなのだと思う。 格闘技という言い方をしたが、十代の頃夢中になったのはプロレスだ。力道山の創設した老舗団体日...
先日、奥田民生とYouTube音楽部門トップとの対談番組があった。コーエンというその音楽責任者が言っていた。 「日本には魅力的アーチストが多数いて素晴らしい。しかし例えば韓国のような小さな国が世界を相手にして音楽を発信しているのに、日本はど...
盛岡での文学フリマでは、予想もしなかったことがいくつかあった。開始早々に私の小説を買うために初めてこのイベントにやってきました、という方が見えられ、とても驚いた。私の地元は関西であるし、あと私が懇意にさせていただいている劇団を通じてかとも思...
盛岡駅を出てしばらく行くと、大きな川を渡った。北上川だ。 北上川といえば僕らは「北上夜曲」を思い出す。誰の歌だったのだろう。ダークダックスとかそのあたりではないか。紅白歌合戦とか、おそらく幼い頃に幾度か耳にしてその印象的なメロディがいつのま...
「弱法師」と書いて「よろぼし」と読む。天才とうたわれ夭逝した世阿弥の長男観世元雅作の謡曲である。主人公シテは俊徳丸。盲目の弱法師つまり乞食である。よろよろと歩くからよろ法師。弱法師は当て字だ。当時乞食は僧の身なりをしている者が多かった。 乞...
人生の途轍もない恐ろしさをまだ思い知る少し前に、浪漫チックにとても好きだった I am a rockという歌がある。Simon & Garfunkel の歌だ。特にその歌詞にとても惹かれ、なんどもノートに書き写した記憶がある。14...
圧巻の一言。 ずっと観たいと思っていて、ようやく観ることができた。映画そのものについてはただもう「よかった」と幾分放心気味に答えるだけだ。 その余韻は長く残った。そして無性に中国への憧れがむくむくと込み上げて来た。久しぶりに思い出してしまっ...
来週の日曜、盛岡に行く。文学フリマに出店するのだ。文学フリマとはつまり文学フリーマーケット、僕も初めて参加するので実はよく分かっていない。コミケの文学版なのかな、という程度だ。しかし作者が自ら自分の作品を販売するというスタイルにはとても心躍...
先日、或る画家の方のギャラリーを見学させていただいた。 間近に原画を拝見できるだけでも幸運だが、その作家と言葉交わしながら作品を味わうのはまたさらに格別だ。 光が映すくっきりした影の輪郭が森の道や積雪の土手に浮かび上がる清冽な情景を精緻に...
映画「マクリントック」を観た。ジョンウェイン主演の西部劇である。かと言って、主人公はガンマンでも騎兵隊でもない。町をしきる実力者と自他ともに認める大地主の農民である。シェイクスピアの「じゃじゃ馬ならし」を基にしたコメディ映画だという。 しか...
梅原猛の著作をきちんと読んだことはほとんどなかった。最後まで読み通したのは能紹介の本くらい。「地獄の思想」もその著書名を知っているだけだった。これは先日古本屋で店頭150円で売っていた中公新書版。発行は1967年だ。新書書き下ろしである。6...
中野信子という脳科学者は面白い。そう思っていた。 BSで「英雄たちの選択」という歴史を題材とした番組がある。歴史ものの番組はいくつかあるがこの番組が面白い。「ザ・プロファイラー」という歴史上の人物をプロファイリングするという番組があるが、ち...
Eテレの「100分de名著」で「平家物語」をやっている。いい。何がいいかって、コメンターがあの安田登なのだ。能楽師ながら、実にわかりやすく読みごたえのある本たくさん書いている。私も「ワキから見る能世界」と「能 650年続いた仕掛けとは」を読...
ミケランジェロ・アントニオーニ監督の「太陽はひとりぼっち」を観た。まずこの邦題はちょっと悲しい。原題は「日食」である。「情事」「夜」に続くアントニオーニ監督の「愛の不毛三部作」と称される作品なのだから、そのまま「日食」或いは「日蝕」で良かっ...
NHK日本の芸能 能「砧」 捨て置かれた女の恨み物語である。京に訴訟のために上った夫から音信が絶えて三年たち、ようやく間もなく帰ると伝えられ、妻は中国故事になぞらえ夫に思い届けよと砧(きぬた)を打つ。砧とはアイロンのように洗った衣服を叩く木...
スマートレターが届いた。一体何がと開いたら、もう30年近く前に自費出版した私の小説だった。添えられた手紙もなく、どのような意図で送付されたのか分からなかったが、汚れて染みの広がる一冊だけしか手元に残っていなかったので、まだ美しいその一冊はと...
ヒロトのブルーハーツに、どんな記念日なんかよりあなたが生きている今日はなんと意味があるのだろう、と叫ぶ歌があった。LiveStandなど正月のライブでは、「記念日」を「お正月」に置き換えて「どんなお正月なんかより」と歌っていた。 正月はただ...
六角獄舎の図面をようやく入手した。近代以前の獄舎については小伝馬町の獄舎の資料が多く残されている。但し、江戸の所在なので規模もひどく大きいし、各藩の獄舎についてはどうしてもわからない。せめて京都の六角獄舎ならばと思い探したがネットではその大...
演技「汚れ」考 〜劇団男魂(メンソウル)「バカデカ 勿忘草」 前に僕が書いた映画シナリオについて、脚本の師匠から「キャストするなら主役はどんな俳優さんがいいですか?」と問われた。シナリオの主人公は使命感などかけらもないやさぐれた刑務官だ。僕...
演劇論は一冊も読んだことはないが、自分なりに悲劇と喜劇の関係については呑み込んだ。きっかけはメンソウルの舞台だが、見ていくとあらゆる悲劇は喜劇に移し替えることができるし、その逆も同様だ。しかし寅さん、チャップリンと言った喜劇が愛されるの同じ...
劇団男魂(メンソウル)の劇「but and」の上映会を行った。もう5年前の舞台映像だが、その力は圧倒的だ。 メンソウルワールド、そのエッセンスである座長にして脚本演出を手がける杉本凌士ワールドと言いかえてもいいのだが、私が惹かれてやまないの...
作家がその物語に登場する人物である「私」として小説を書くとき、作家は人物に憑依され「私」となる。しかし例えば群像小説など、それぞれの登場人物が体験する主観世界を併存させて物語るときなど、作家は「私」ではなく、無主体?の超越的な人格として、よ...
國分功一郎『中動態の世界 意志と責任の考古学』(医学書院) 斎藤環書評 <リンク> 我ならざる我、私を支配している自動回路が暴かれて、私たちの世代が時代の空気価値観としてそのままに吸収してきた近代的自我や主体性理論がすでに効力を失って久...
昨日、京都演劇祭に出かけた。数年前にも一度参加したことがある。そのときは確か、府のコンクールで受賞したという高校演劇部の劇を観たのだ。それは水上勉原作の有名な戯曲で、とても見応えがあって驚いたのを覚えている。今回は、中島貞夫監督シナリオ塾で...
凄い舞台を見た。感想もすぐにはまとめられなかった。劇団男魂(メンソウル)の「BUT AND」だ。2014年第15回公演の収録映像を見せていただいたのだ。 なんと言えばよいか、杉本舞台のテイストは最高なのである。素晴らしい。いつも男魂の劇をこ...
ここにも記したがNHKで久しぶりに能を堪能し、そのまま余勢を駆って安田登の「能-650年続いた仕掛け-」を一気に読んだ。面白かった。と、さらに能に造詣の深い著名なある随筆家を特集するテレビ番組があり、録画しておいた。名前はよく見知ってはいた...
▼ Anly – MANUAL ▼ The Blue Hearts – Too Much Pain ▼ 友部正人 – お日様が落っことしたものはコールタールの黒 ▼ 熊木杏里 – 朝日の誓い ...
卒都婆小町は観阿弥作の能楽である。観阿弥は能楽を確立した世阿弥の父だ。 美少年世阿弥は将軍義満から特別の寵愛を受け、上流階級の中で成長していったのだが、その環境基盤を築いたのは父観阿弥である。観阿弥はもともと奈良大和で様々な芸を披露する芸能...
ほんの短い期間だったが、こっそり事前投票事務のバイトをした。2回目だが久しぶりに会う顔もあってちょっとした同窓会気分だ。市井の人たちの中に入るのは楽しい。立場や役割でふんぞり返っている滑稽な男たちよりも、組織や権威とはかかわりなく実は太々し...
壇ふみが父檀一雄が滞在したニューヨークを訪れる。そこで壇ふみはそれまで読んでいない父の「火宅の人」を読むことになっているのだ。「火宅の人」は檀一雄が愛人との生活を赤裸々に記した事実上の私小説とされている。壇ふみは父の没後もその長編を実は読ん...
男魂の舞台映像を観たせいで、「惡の華」を別なアングルから見ることができるのではないかと思った。先に書いたように、「惡の華」は暗く荒涼とした鬱の世界が描かれている。しかし、悲劇は喜劇でもある。それは描き方次第。だから男魂作品は喜劇と悲劇が折り...
劇団男魂(メンソウル)の第11回本公演「GRAPEFRUIT MOON」をDVDで観せていただいた。素晴らしかった。 劇のあれこれ書きたいのだが、あまり内容に触れるとネタバレになってしまう。しかし、よい作品はあらかじめあらすじを知っていても...
Asa-Chang&巡礼のhanaの美しさに惹かれて辿るうちに、押見修造に出会った。若い人の間ではよく知られた漫画家なのだろうか。先日、若い友人が「開放倉庫」に連れて行ってくれた。メジャーになる前、もう何十年も前のvillage ...