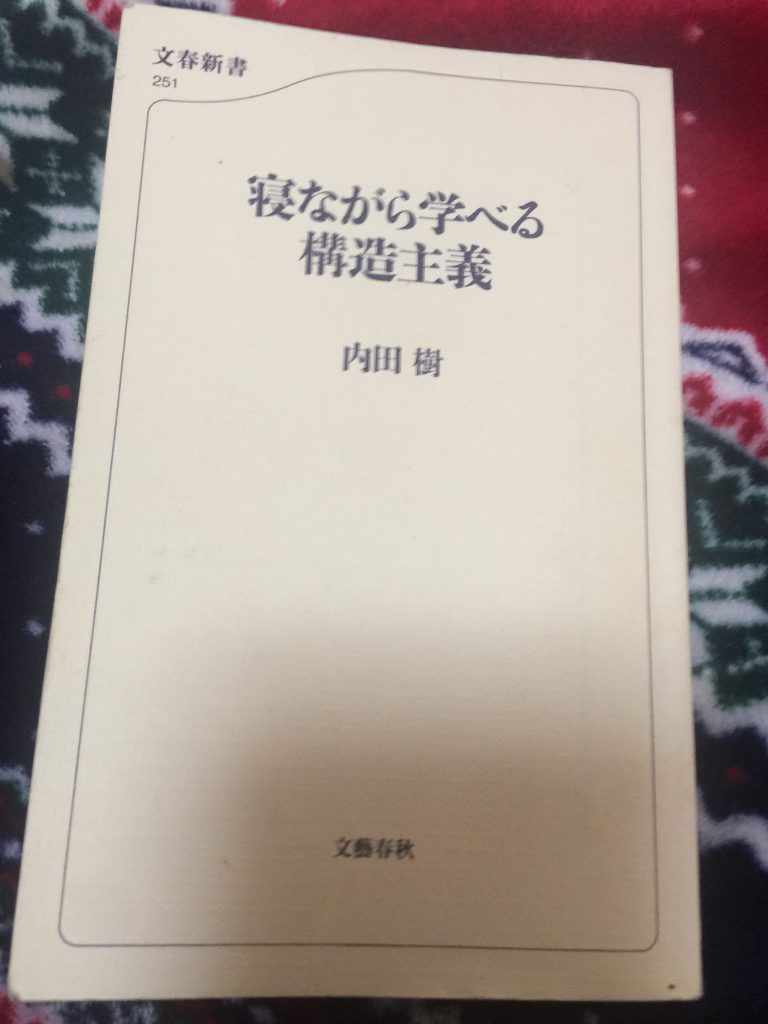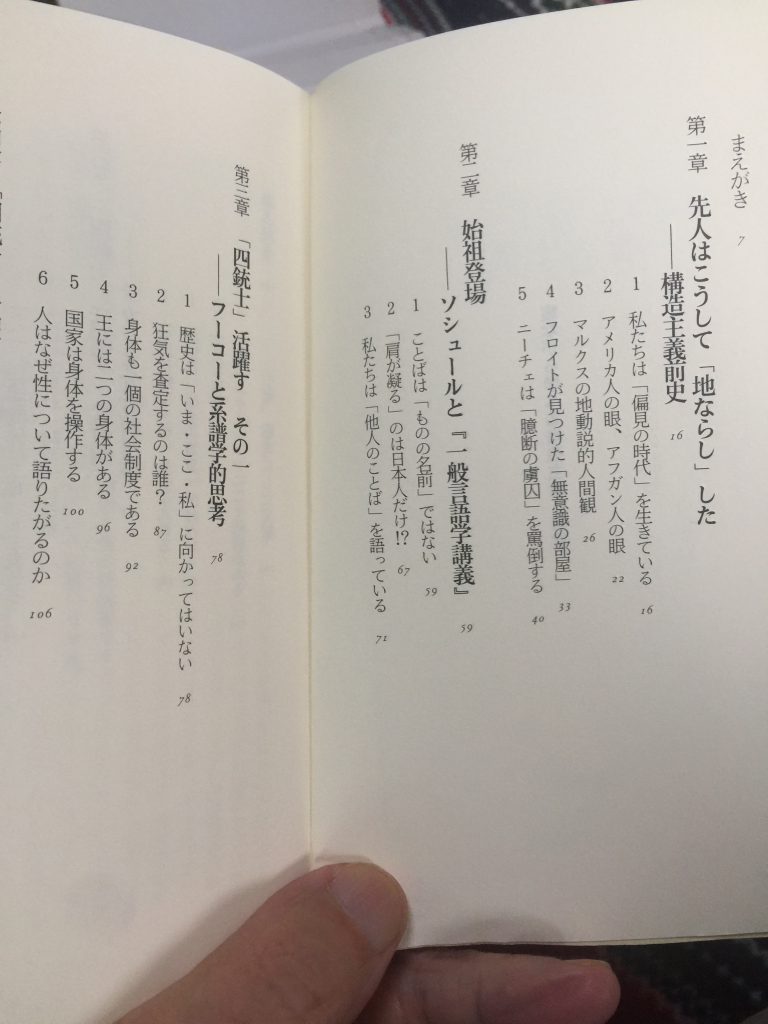内田樹「寝ながら学べる構造主義」2002
こういうタイトルの本はまず敬遠する。コンビニに並んだこの類のお手軽本は大方「わかった気になる」だけで、本当は全然わからない。というか、つまり「わかった気になる」という一点でダメだ。物事は、わかれば一方でわからない部分が浮上し、もっとわかりたくなるものだ。「なるほどよくわかった。でも、ここのところはどうなのだろう」疑問まで行かない小さな引っかかり。「どんな違う意見があるのだろう。逆の立場からはどう言っているのだろう」知ればもっと知りたくなる。「そうだったのか。しかし、ここはどうなのだろう」違うところへ視線を動かしたくなる。深さを角度をそして見方を変えたくなる。そうして少しずつ豊かに大きな全体像が見えてくる。だから、「わかった気になり、もうわかろうとしなくなる」というのは最悪だ。「目からウロコの〜」「誰も書かなかった〜」「本当は〜」これらのタイトル本は大概、人間を馬鹿にさせる。際限なくそれ以外の見方に誘う物事の深みを消し去って、のっぺりと一面的で偏狭な切り口で「俺は分かった」という幼児的万能感満載の安直ドーパミンに溺れさせる。
しかし、この著者は内田樹だ。僕は構造主義を知らない。ペラペラとめくってみた。面白そう。で、腰を入れて読んでみた。すごい!面白かった!一気に読破した。
構造主義前史として挙げられた先駆者がマルクス、フロイトにニーチェ。マルクス、フロイトは昔一時期はまった。ただ、構造主義先駆けとしての見方はとても新鮮だった。つまりマルクスに関していえばその階級社会観はあくまで社会認識の方法として見るだけで、個人にとっての階級はそれこそ理性主体中心に疎外論としてしか見ていなかった。今頃になってマチウ書試論最後に書かれた「関係の絶対性」を想起した次第。フロイトの無意識論もあくまで精神病理の仕組みを解くための理論として理解していたので、人間がそもそもの成り立ちとして我ならざる無意識を自分として意識するのが人間だという理解の方法はとっていなかった。哲学として読んではいなかったということだ。ただ、ニーチェについては拒否感が先立ってこれまで読んでいなかった。しかし、超人思想でぶっ壊れるまでに一つ一つ多数意見の信仰を壊した部分はとても共感する部分があった。いつも思うのだが、例えば歴史上の過去は、「過去の現在」である。つまり、現在は過去と未来を前後に従えているが、過去だってそうだ。例えば幕末の天誅組挙兵は現在から見たら過去であるが、1863年8月17日そのときにはまさに現在であり、その時点に過去があり未来があった。つまり、縄文時代の衣服を見ると、古いと感じるのは現在からみて古いのであって、当時その時点においては決して古くない現在の衣服である。こうして見て行けば、地域と時代の差による評価基準、受け止め方の相対性の前にガラガラと価値は崩れ落ちる。そのあとで残るもの、それらを超えるものとしてニーチェが提示したものは意外と情けないのだが。
それにしても、内田樹の文章は魅惑的だ。どうしてだろう。単にわかりいいというだけではない。とらわれなく軽やかで、何かつややかな「いい匂い」がする文章。物書きだな。そう思う。
そして構造主義の父ソシュール。この章はさすがにわかりにくくて、一旦読み終えてからもう一度読み直した。「ことばとは『ものの名前』ではない」先に指し示される名もなきものや概念があり、それからそれをあらわす名前=言葉が生まれた、のではない。漠然模糊としたものから言葉が切り取ってそれがものや概念になる。これは凄い。これは僕は体験的にわかる。詳述はできないが、近いものとしてはキリスト教が日本に流布される経過がわかりやすい。初めキリスト教は、その教義を日本にすでにあった言葉で広めようとした。天国は浄土、悪魔は天狗とした。広まるのだが、キリスト教は浄土宗の一派とされてしまう。とても世界観が似通ったものがあったからだ。そこで教会側は、既存の宗教用語をいっさい使わない道を選ぶ。それでは布教できないという意見もあったという。そのまま原語(ポルトガル語)の音を使った。当時の教義教科書にあたる「どちりなきりしたん」を見れば、オンパレードである。かてきずもCatechismo(教義)、がらさGaraca(恩寵)、ばうちずもBautismo(洗礼)、ぽろへゑたPropheta(預言者)、くるすCruz(十字架)、すぴりつSpiritu(霊)、ぐらうりやGLoria(栄光)等々きりがない。それらを初めて聞いた日本人はそれまで日本語になかった言葉であるから「まったく」意味がわからない。確かに似た日本語はあるが少し違うらしい。つまり、その意味をあらわす日本語はないらしい。困惑したはずである。それでもそれから爆発的に信者を獲得して行くのであるから、布教者は相当に優れた説教者であったのだろう。つまり、言葉が隈取って、意味を確定する。言葉が先に規定しているのであって、世界を自由に言葉を使って語っているというのは幻想なのだという。さらに、語るものも実は自身から出たものではないことを明かす。どこに自分はあるのか、ということだ。私は他人でできている。私は社会通念社会意識によってできている。あらゆる思考をつかさどる言葉さえ、言わばひとつのアングルにすぎない、ということだ。
面白い。構造主義が実存主義を駆逐したという意味がよくわかる。それはすでにフランスでは60年代に決着がついたというのだが。
そしてフーコー。構造主義四銃士フーコー、バルト、レヴィストロース、ラカンというが、フーコーがいちばん分かりやすかった。というか、他の三人特にラカンは「わからなかった」。今回はここまで。フーコーはつかめる気がするし、とても惹かれる。他の三人は置いて、フーコーをまた別の入門書から読むつもり。「狂気の歴史」「監獄の誕生」は大著だがまとめ本でも見つけたい。
いや、面白かった。僕にとって哲学は、学生時代に読んで世界が一変した弁証法(三浦つとむ)、それから三十代になってから仕事の混沌(二者関係の面接と社会関係としての意見提出)を救われた共同幻想論(吉本隆明)が依然脳みそに根を張っているが、構造主義はそれ以来の衝撃を含んでいる気がする。あくまで傍証としてなのだが。