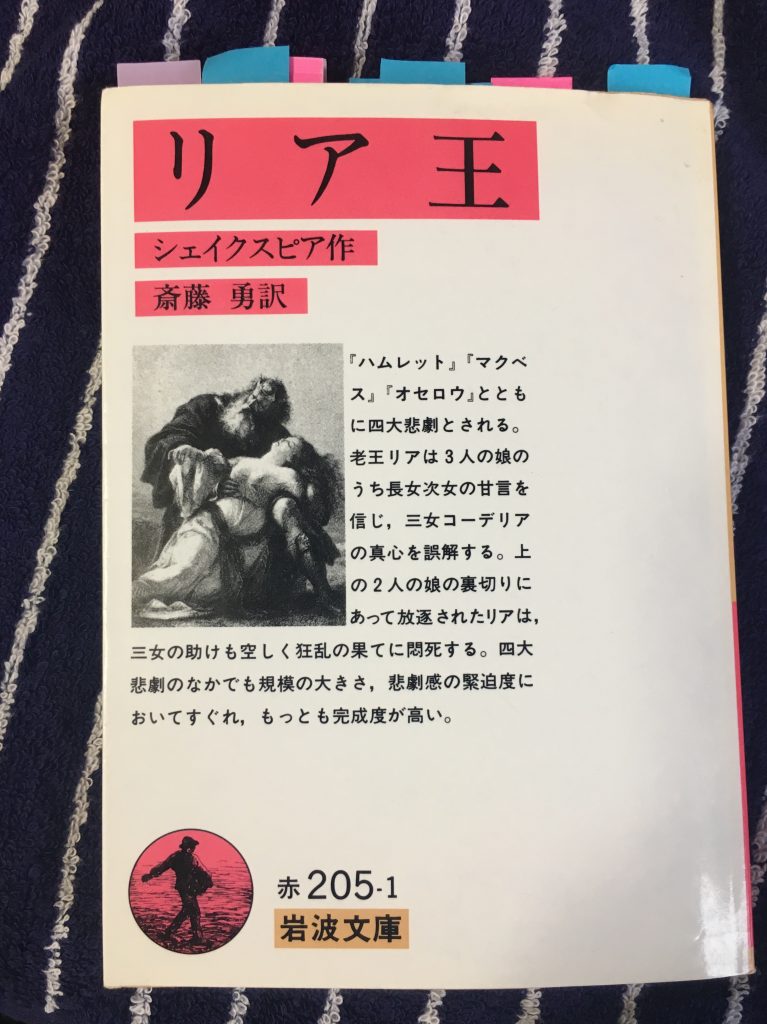シェイクスピア「リア王」1606
リア王の王権譲渡をめぐる約ひと月の騒動の間に関係者のうちほとんどが非業の死を遂げ、生き残るのはほんのわずかだ。この凄まじい急転直下の崩壊はどういうことか。
冒頭リア王は、旺盛な我が権力を生前に譲渡するため国土の分割を自身への賛美の度合いで決めようとする。これが崩壊への幕開けとなるのだが、臣民を預かる王とは思えない愚かしい戯事である。おそらく王は、権力は盤石のうえ娘たちの婚姻も進み、栄華の絶頂にあったのではないか。まさしく慢心である。長女と次女が口先だけの美辞麗句を並べ立て王への敬慕を口にしてもうぬぼれに酩酊するばかりだ。彼女らがのちには自身を一人嵐の荒れ野に追放して発狂させるだけでは飽き足らず、「おいぼれ」「きちがい王」と口ぎたなくののしり、果てにはその暗殺を謀る者たちであるとは微塵も感じ取ってはいない。おごった侮りは、かようにも人の目を節穴にするのである。
その二人の娘たちであるが、互いに反目しながらも父王の権力を奪い取るために表面上共謀はするが、やがて男をめぐって憎み合い破綻に至る。美しい次女リーガンは長女ゴネルリの寵愛を受ける臣下オズワルドを言葉巧みに誘惑し、そそのかして殺人を仕向ける。姉妹はエドムンドの姦計とも知らず互いに彼を我がものにせんと対立し、最後には長女が次女を殺害したうえ自害して果てる。無惨である。
次女リーガンの夫コーンウェル公は王の忠実な臣下グロスター伯を謀反人と決めつけ両目をえぐり追放するが、そのあまりの蛮行を押しとどめんとした自身の従者によって剣で負傷せられ絶命する。その従者を背後から襲って殺害したのは妻リーガンであるが、彼女は夫の死を悲しむどころか、むしろ好機到来と男を操るため亡き夫の権力を餌に利用する。浮かばれようがない。
グロスター伯が謀反を企てているとコーンウェル公に讒言したのは、なんとグロスター伯の庶子エドムンドである。哀れな被害者然としたグロスター伯であるが、彼は先立ってエドムンドの策略で誠実な嫡子エドガーを反逆者と思い込み、憎しみのあまり殺害せんと追っ手を差し向けているのだ。彼は失明して荒野をさ迷ううちに、嵐の小屋に気の触れたリア王とともにいる狂人のふりをしたエドガーと出会い、ようやく一部始終を理解して絶命する。軽々しく人を信じる愚か者と私生児とは言え実の子であるエドムンドから陰で嘲笑われているグロスター伯であるが、九年間エドムンドを外国へ追放していたうえ、望まれて生まれたわけではないふしだらな臭いのする子だと彼の面前で友人伯爵に紹介している。エドムンドはいたたまれない屈辱を味わったにちがいない。彼を復讐と野心の虜にさせたのは、おそらく無自覚なまま非道な仕打ちを平然と重ねていた父グロスターであったと言えるかもしれない。
リア王物語は王と三人の娘をめぐる物語と紹介されることも多いが、何よりもエドムンドがその発端となって巻き起こす王家をめぐる権力の野望、謀略、陥穽そしてどろどろとした愛憎絡み合う人間関係の崩壊物語である。
だから一方の主役はエドムンドである。
エドムンドは讒言謀略と狡猾な知恵を用いて、王権に関わる者たちを次々に追放し死に追いやる。彼が突くのはその人の弱みだ。欲に駆られ、或いは妄信し、破滅して行く人々はエドムンドの邪心をトリガーにしながらも自身の煩悩をブースターにして悲劇を拡大させてゆく。そのほとんどが被害者であり加害者でもある。
冒頭述べたリア王の慢心もそうであるし、グロスター伯の軽挙妄動を見れば、到底ただの被害者とはいいがたい。唯一王権を有し生き残ったのは長女ゴネルリの夫オールバニ公であるが、彼は妻から気が小さい意気地なしの馬鹿者と散々なじられる人物であり、騒動に危機感を抱き介入するのは悲劇がとどめようもなく拡大したあとである。対処不能になるまで先送りした結果ではないか。
そしてコーディリアである。
彼女はまず、父王が求める賛辞を拒否する。傲慢な父を烈火のごとく激怒させるその発端だ。彼女は、なぜ心底敬愛する父に愛情の言葉を述べるよう求められながら nothing としか答えなかったのか。彼女の心情は、歯の浮くような姉たちの言葉を聞きながら独り言ちる台詞に込められている。「孝行はするが、だまっていよう」「わたしの孝心は舌よりもたしかに重みがあるんだから」彼女は、姉たちが言葉とは裏腹に内心では父を蔑み疎んじていることを知っている。それを真に受け、いい気分でふんぞり返っている父を前にして、何を語ろうとも姉たちの美辞麗句に紛れ同じものと扱われるのが我慢ならなかったのだろう。口ではなんとでも言える。違うのは心であり行いである。姉たちは孝行の言葉を述べることはできても、その心はないから行為もできない。だから私は姉たちのできない行為を以って示そう、というのだ。姉たちは言葉を示すが行いは示せない。私は行いを示すことはできるが言葉で示せない。しかし言葉よりも心がはるかに大事なのだと小さくつぶやいている。そしてコーディリアは思ったのではないか。父にそれがわからぬはずがない、と。そこがすべての始まりだ。父は激怒した。それはただの怒りではない。なだめる忠臣ケントを追放し、コーディリアをお前など生まれてこなければよかったと罵り二度と顔も見たくないと勘当してフランスへ追いやる。この常軌を逸した怒りは、侮辱された恥をかかされたという逆上に見える。リア王はもとより三女をもっとも愛していたというのは、娘たちの中でもっとも私を敬慕する者と知っていたからではないか。だから、姉たちの見え透いた甘言がコーディリアの沈黙に勝るものではないと本当は知っていたのではないか。それでも、甘い言葉は心地いい。酩酊させる。いい気分になっているところに、コーディリアが冷や水を浴びせる。口先ではなんとでも言える。それよりも行為で現れる心こそがはるかに大事ではないか。それなのに甘い言葉に脂下がっているとは情けない。リア王は赤面し烈火のごとく怒る。そんなことははじめからわかっている。わしは王だ。これくらいのたわごと許されるはずではないか。王である父に恥をかかすとは何事か。そういうことではないか。
コーディリア生来に持つ生真面目な頑固さゆえの空気を読まぬ正論が、浮かれているリア王の矜持を無残に砕いたのだ。コーディリアはそうしたリア王の脆い自尊心を理解できなかったのではないか。最後コーディリアは敗北覚悟でリア王救出のためフランス軍を率いて上陸し、あっけなくリア王とともに捕らえられる。そしてエドムンドの命により獄中で虚しく謀殺される。リア王がはじめに嘆いたコーディリアの頑なさが招いた最期である。
こうして見ると、シェイクスピアという作家の巨大さに圧倒される思いがする。人間心理に対するかくも深い洞察を背景に、権力への欲望と絡み合う個性際立った男や女たちが繰り広げる息呑む人間ドラマを編み上げ、それを超絶巧みな言辞を駆使して詩劇に結晶させるとはまさに人間業と思えない。
ソポクレスから誘われるようにシェイクスピアにたどりついたが、この系譜はドストエフスキーにやはり結ばれるように思えてならない。しばらく「ハムレット」などシェイクスピア悲劇を堪能してから、ロシアに向かいたい。