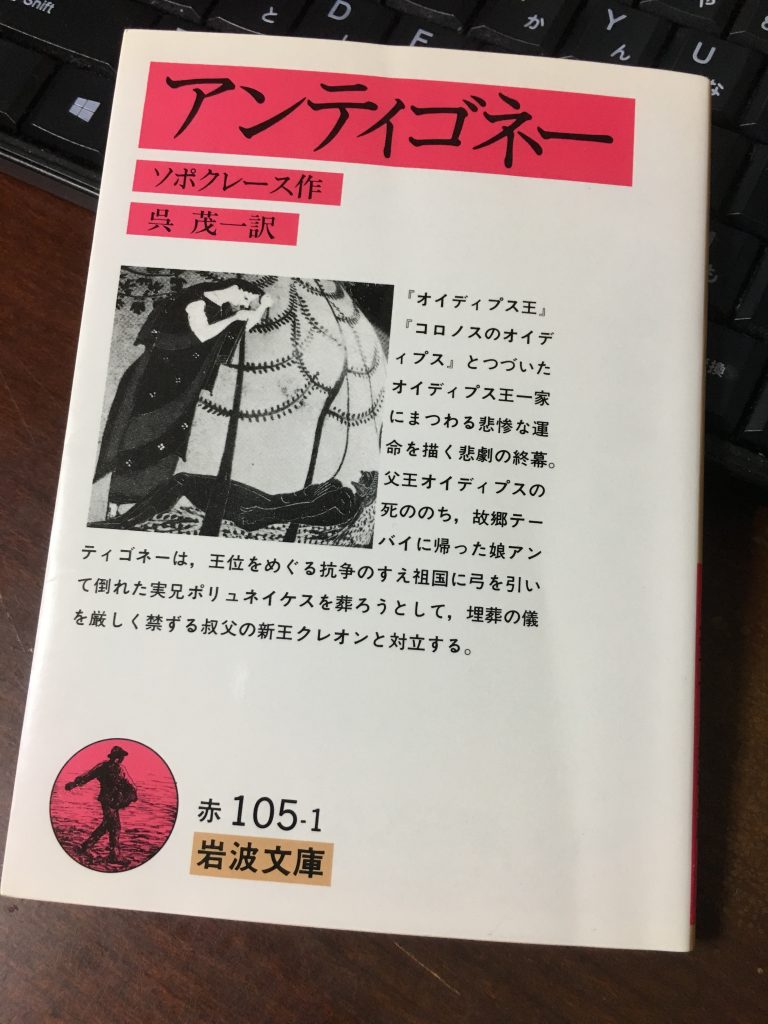ソポクレス「アンティゴネー」B.C.441
どうしても気になり、ソポクレス自身の「アンティゴネー」の戯曲台本を読んでみたくなった。長く借りていた本を抱え県立図書館へ向かったが、長期延滞の小言をもらうだけで図書を借りることはできなかった。やむなく、BookOffまで出かけ、呉茂一訳の岩波文庫を入手した次第。
展開がスピーディで凝縮されている。登場人物はわずかだ。先に読んだサマリーも呉茂一によるものだったので、すんなりとそしてしっかりと読み進めることができた。幕場の転換はないが、コロスという合唱隊が時間系を区切る。詩の斉唱ならば能の謡と同様だ。謡は常に控えてシテワキの言葉に絡み物語を深め強めるが。
そして「アンティゴネー」物語そのものについてだ。古典文学に対しては、現在の地平にも響く普遍の部分と、近代の勝手な解釈による早呑み込みを注意深く識別したいところだ。同じ言葉であらわす事物や概念にしても、現代日本と古代ギリシャにおいては意味合いがまったく異なって当然だからだ。しかし当時のギリシャ社会も戯曲文化についても無知であるから実は雲をつかむようでとても歯がゆい。だから、結局はただ直感に頼ることになる。
しかしシェイクスピアを読んだときと同じ奇妙な感じがするのだ。時代や民俗文化の違いがむしろ引っ掛からず、なんとも言いようのない不思議な無名の読後感が心にとどまり離れない。
どうにもその物語が心に引っかかる。単純に呑み込めない。この物語には何かがある。そう思えるのである。そう強く感じるのは、ネットでアンティゴネー上演劇の短い予告映像を観た際に「家族愛」というコピーの文字を観たからだ。違う。強い違和感を覚える。それはあまりに無残な矮小化に思える。ならばこの物語の核となるいのちは何なのか。この物語が呼びかけているのは何なのか。それをずっと心で尋ねている。
クレイオンを残虐な暴君ヒールとして、アンティゴネーを心優しく勇敢な美しいベビーフェイスとして観るのは物語の根を否定する理解の仕方ではないか。クレイオンは善君たらんと真っ当であるし、アンティゴネーはそんなに薄っぺらな偽善をまとってはいない。
なにより彼女の亡兄ポリュネイケスへの思慕についてもだ。それは一般的な兄弟愛の矩を超えている。一般的な兄弟愛ならそれを心に秘しながらも耐えて国法に従うのではないか。彼女は処刑覚悟だ。それが愛情であるなら彼女に特別特殊な思いが多分に含まれていたはずなのである。だからと言って性愛的な紐帯に結ばれているとは到底感ぜられない。彼女を奇矯な反逆行為に導いたのは「兄」ではなく、兄の「死」だったのではないか。
もちろん兄への思慕はあったのだろう。しかし彼女はクレイオンから行為の動機を問われ、ポリュネイケス個人への愛着を訴えたりなどしない。彼女はポリュネイケスが見せしめのため野ざらしで横たわりその亡骸が鳥や野犬に喰われようとしているのが耐えられなったのだ。それは「兄」への冒涜というよりも、「兄の死」そのものへの冒涜と映ったのではないか。
そもそもはじめから彼女は処刑を覚悟し予想して行為に及んでいる。アンティゴネーを動かしているのは「家族愛」などではない。そんな空虚な絵空事ではない。呪われ不幸に塗れた一族の悲劇の果てに訪れた「死」の尊厳への侮りが彼女は許せなかったのではないか。一族が背負わざる得なかった不吉な宿業に苛まれ、彼女はずっと生にあっても死の近くを生きてきたのではないか。そして「死」への冒涜が許せなかったのではないか。それは死の側からの思想、死の思想だ。もとより生あるこの世における善悪倫理や苦楽の中でしか生きていないクレイオンには理解しようがなかった。彼にとって彼女は理解不能な死に取り憑かれた虚無の狂人だったのではないか。
実の父親を殺し、その妻、つまり母親を我が妻としたオイディプス王の彼女は娘である。出自の始まりから罪を負っている。義の人でありながら罪人となり自らを罰し追われた父が亡くなり、彼女とその桎梏を同じくする兄弟二人も相討ち合って死んだのだ。その重すぎる運命を同じくする者を次々に失くし、今やただ妹一人だけだ。だから彼女は、もう地上の軛から解放され一族が集う天上に遥か惹かれ、もはや地上に望みを消失しているのではないだろうか。
つまり死は彼女にとって暗く怖ろしい一切の終結ではなく、謂れなき辛酸の日々から解き放たれる歓喜への扉だったのではないか。死は辛すぎる旅がようやく終わる、そのための天上帰還の門だったのだ。だから謂れのない塗炭の重荷から救済される扉であるその死の尊厳を貶めるクレイオンの仕打ちが我慢ならなかった。死の尊厳を冒涜するクレイオンが許せなかった。それほどにアンティゴネーにとってその人生は辛く耐えがたいものであったのだ。権力を手に浮かれたクレイオンにはそれがわからなかった。
ここで想起するのは、旧約列王記のエリアの物語だ。王アハブと偽預言者数百人にたった一人で立ち向かい、エリアは追われたどり着いた荒野で命が絶えるの願って神に訴える。「主よ、もう十分です。私の命を取ってください」そのまま倒れて眠ると天から使いがやってきて、パンと水を与える。そして彼を起こして言う。「起きて食べよ。この旅は長く、あなたには耐えがたいからだ」それは翻訳の妙に過ぎないのかもしれないが「この旅は長く、あなたには耐えがたい」という言葉に私は心深く動かされた。これが「耐えるのはとても大変だ」とか「耐えられないかもしれない」だったら、それほどに響かなかった。天使は「あなたには耐えがたい」とはっきり言っているのだ。人生とはそもそもが耐えることができないほど辛く、そして長いものだと宣告している。御使いは分かっているのだ。その苦しみをわかっているのだ。この言葉にどれほど救われただろう。
それを思い出すのはオイディプス家の重荷背負った人生もまた、長く耐えがたい旅であったはずだからだ。希望や肯定に悪罵を投げかける者が悪であるとは限らない。ヨブの呪い言が、まさに耐えがたい長い旅故であるため神は許された。ヨブの悪罵をたしなめる偽善者を神は強く非難された。この世の桎梏を背負い歩むことを選んで生まれた魂の勇者がたどった忍土での旅路の辛酸に、死に際しときにいたわりやねぎらいで祝福されるのかもしれない。
アンティゴネーはもちろん、オイディプスさえその引き受けた辛酸と塗炭はこの世故のものである。だから彼女は天上において一族は罪になど問われないことを知っている。まして国法など、その時代、その国家が定めた相対の定めにすぎない。それを彼女が心底に得心しているのは、やはり否応なく罪を人を世を尋ねざるえなかった重荷のせいだ。栄光のクレイオンには知り得なかった。
悲劇というが、もともとそういった分類など当時はなかった。物語である。魂を揺さぶる普遍の物語である。