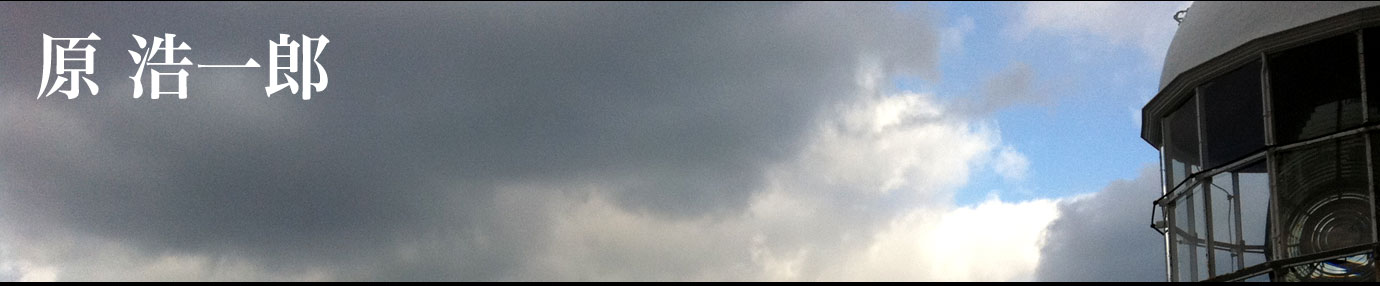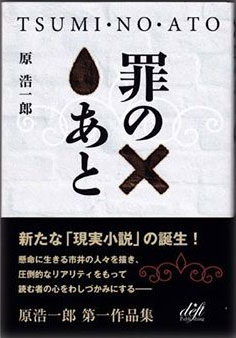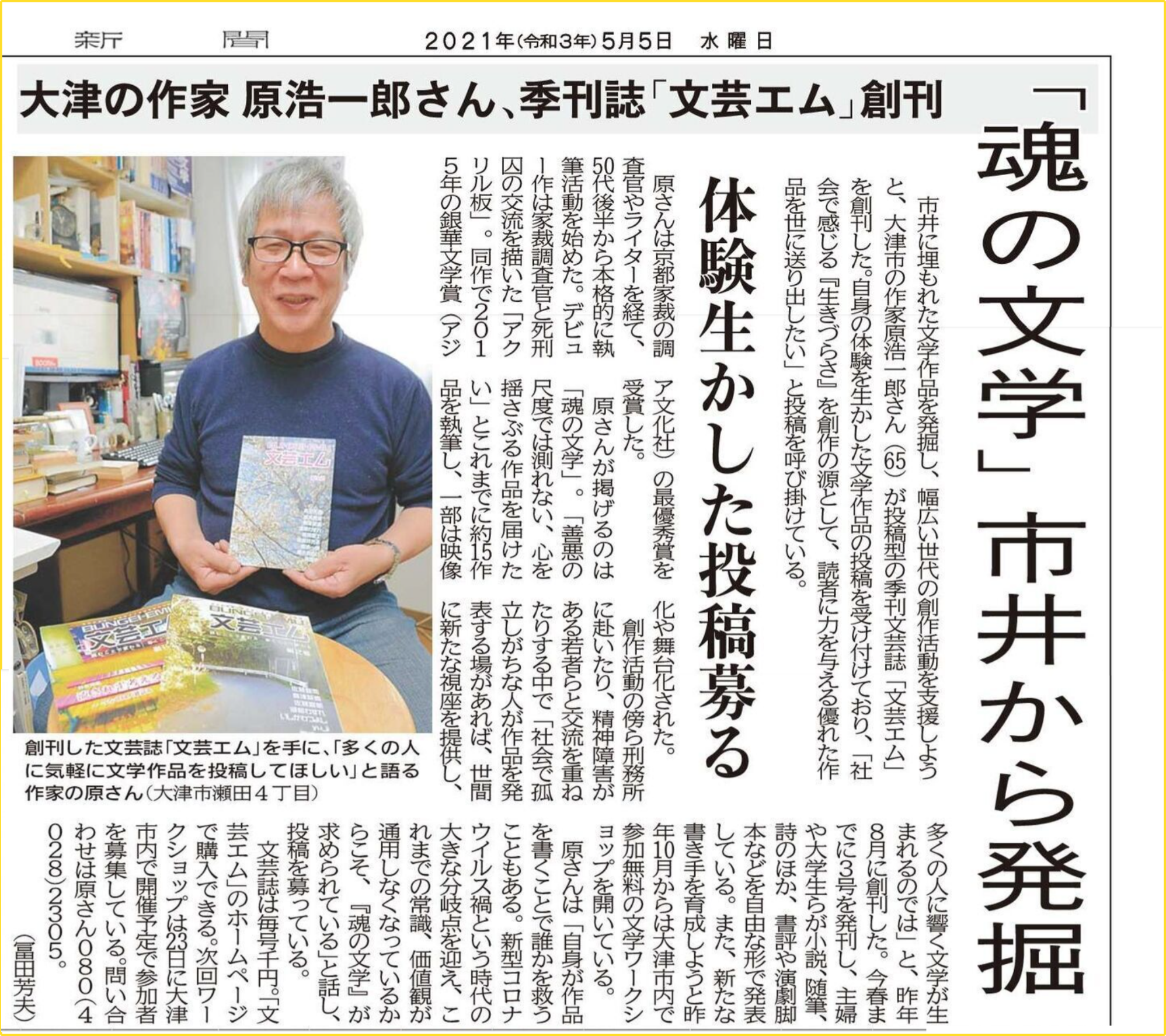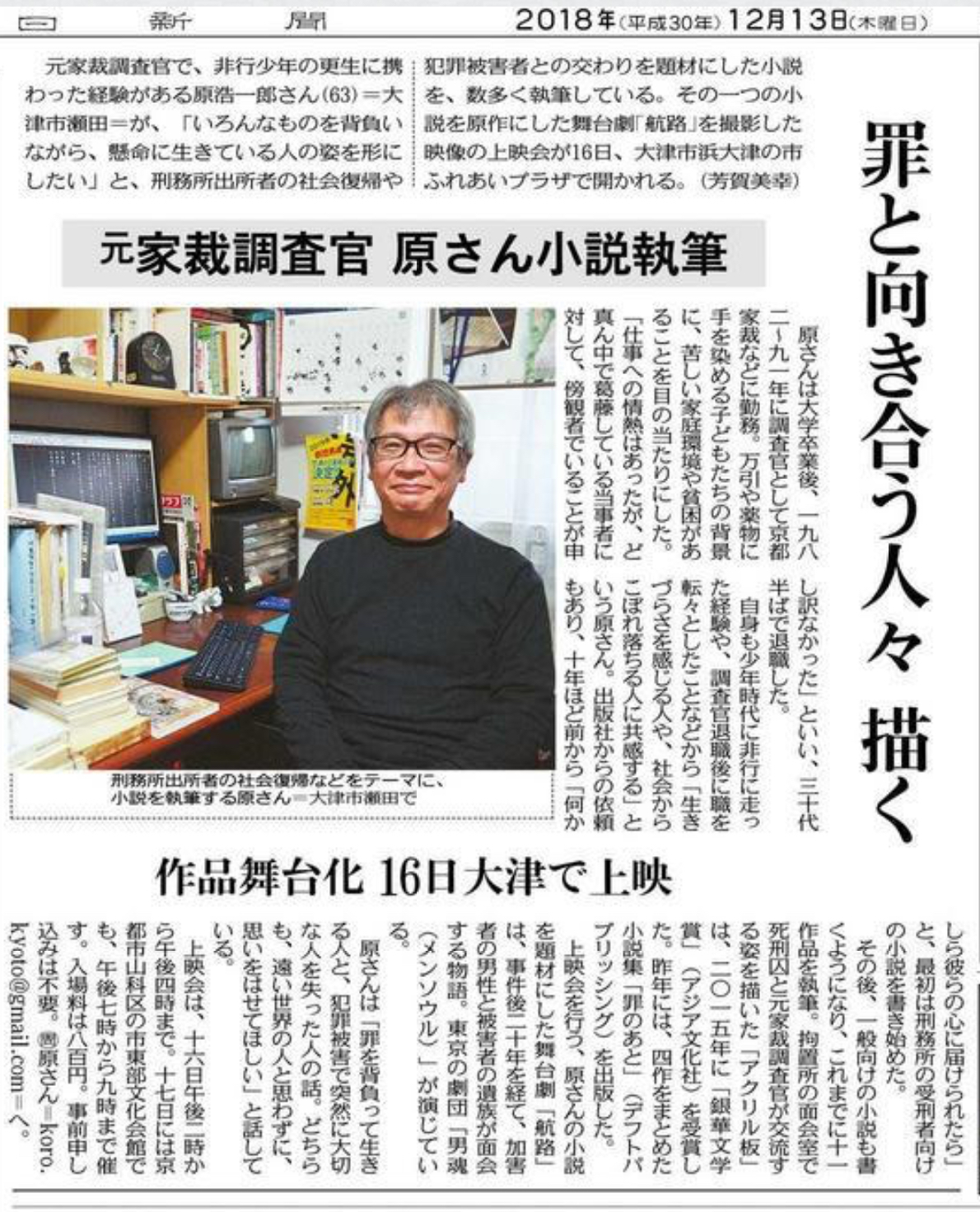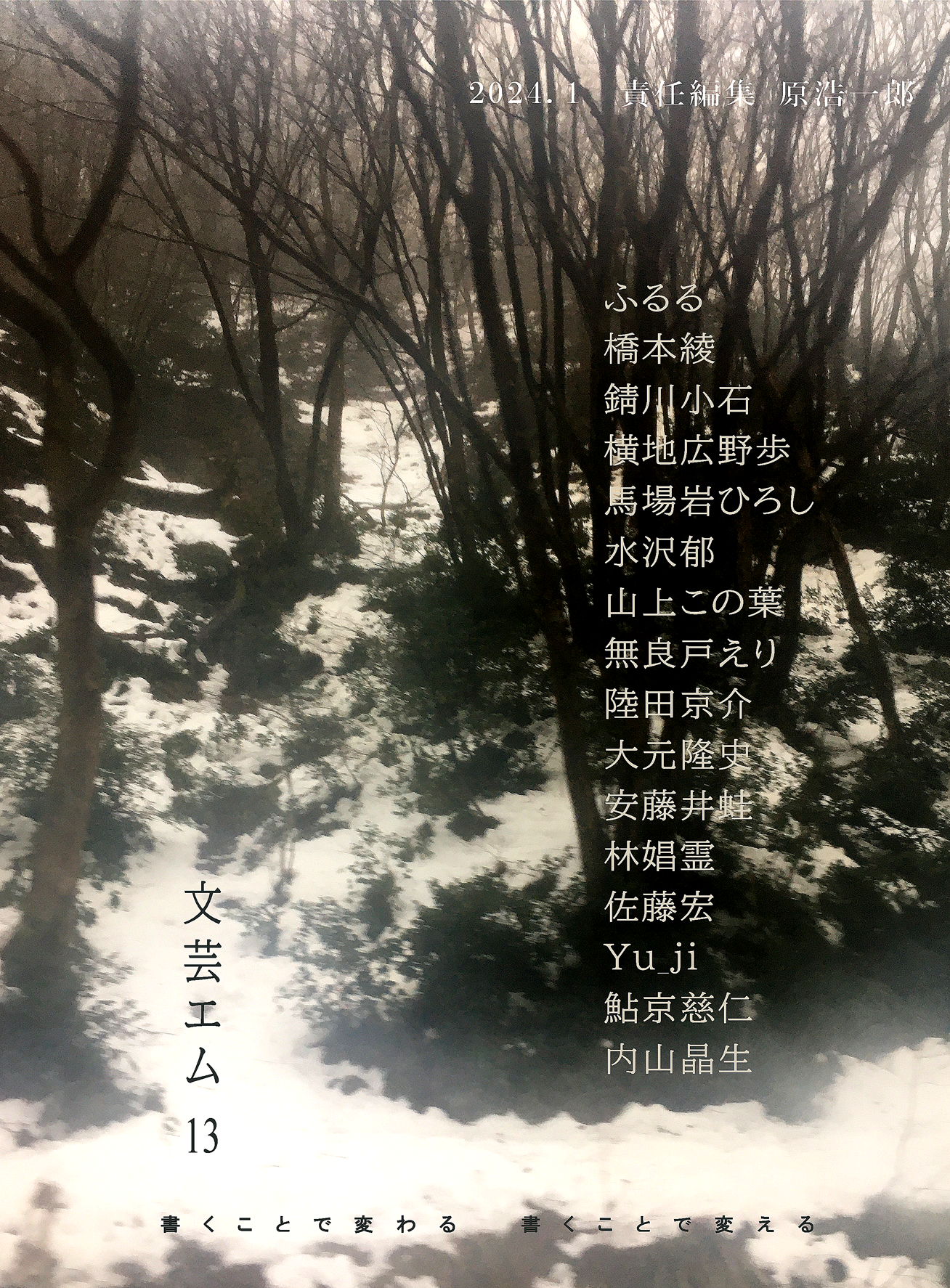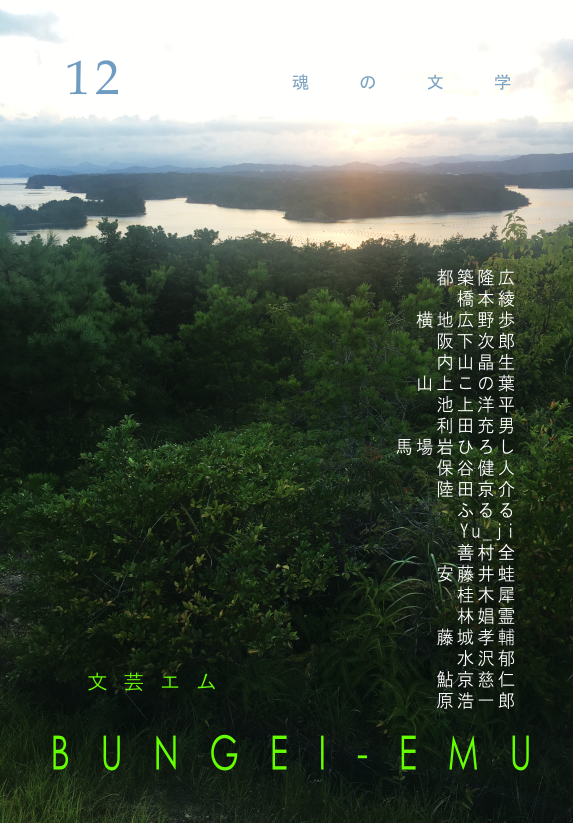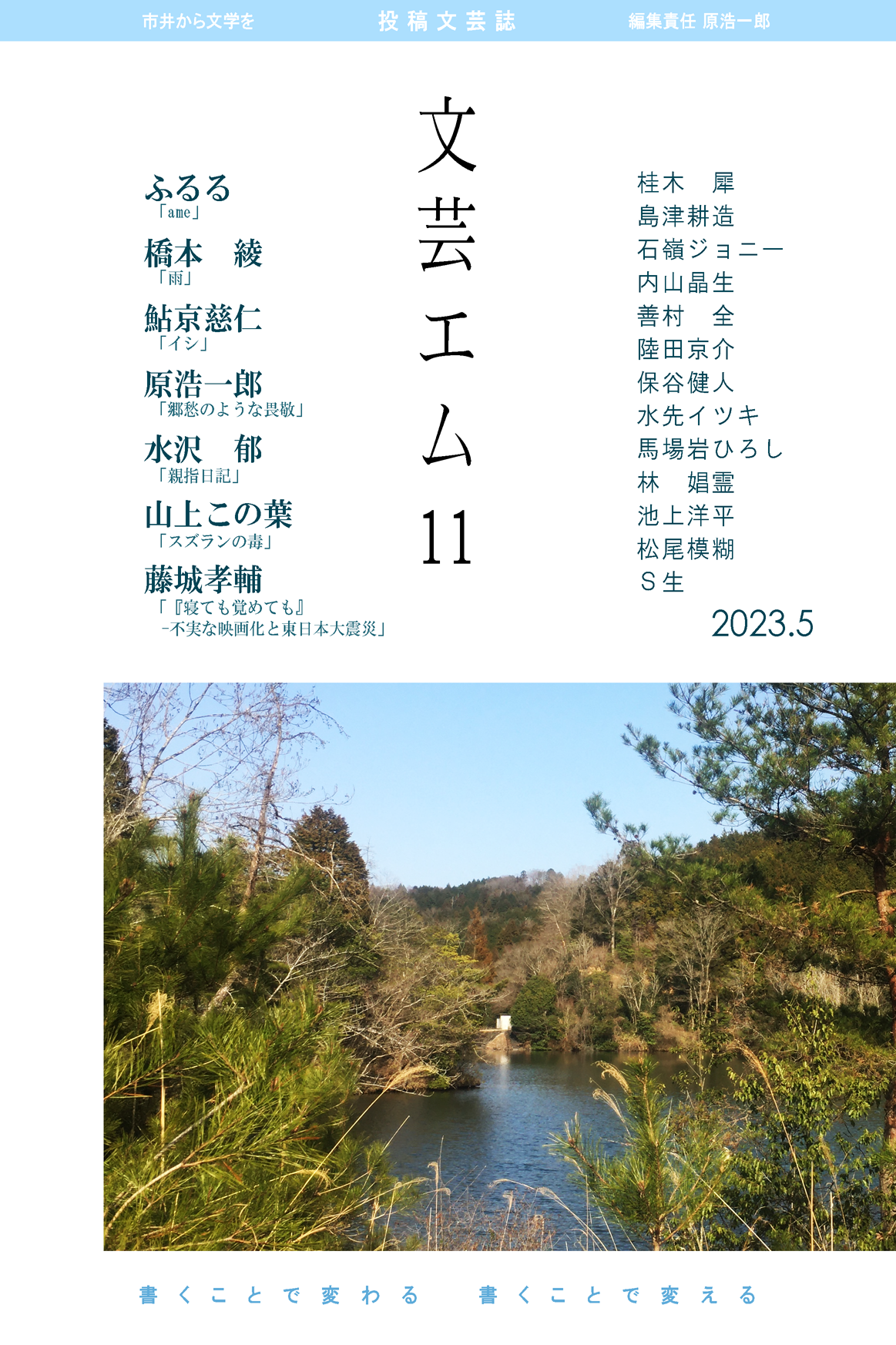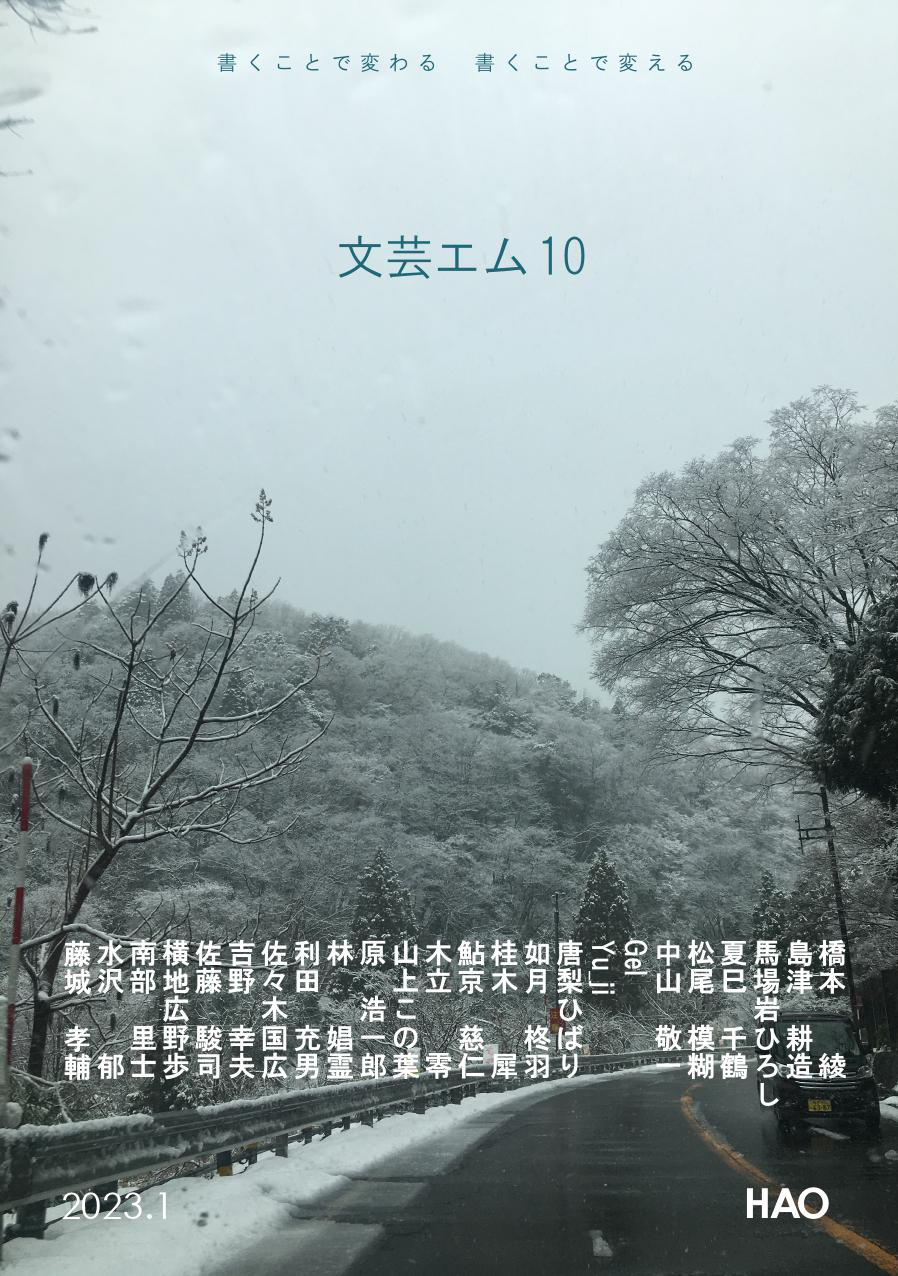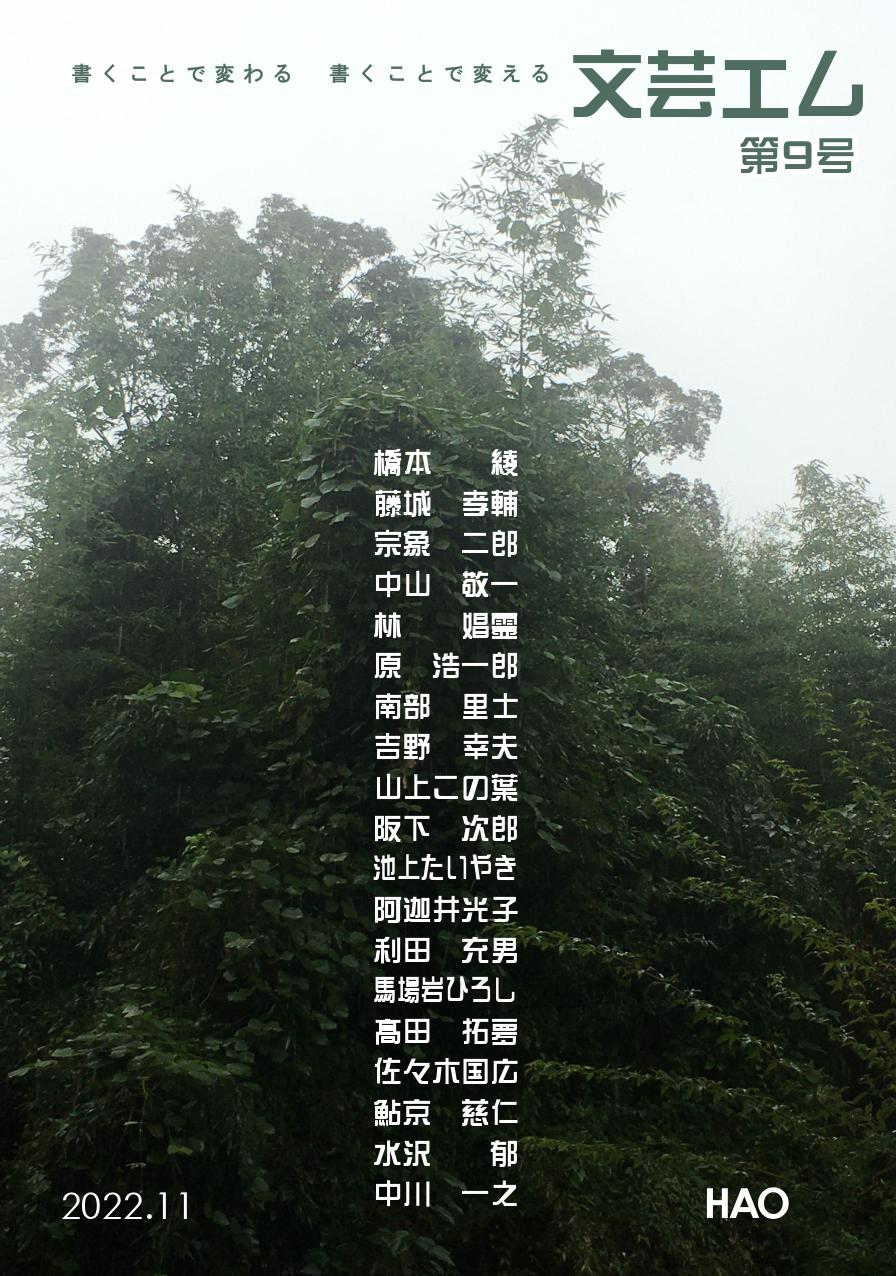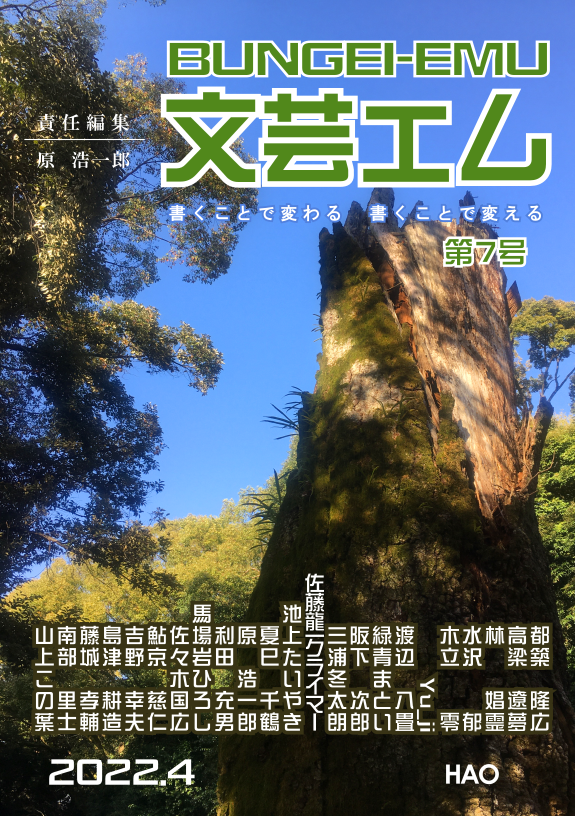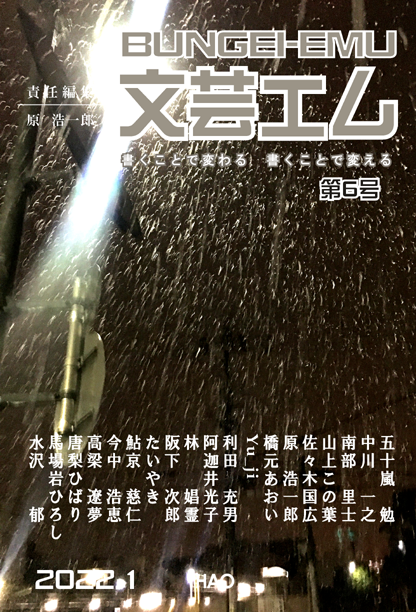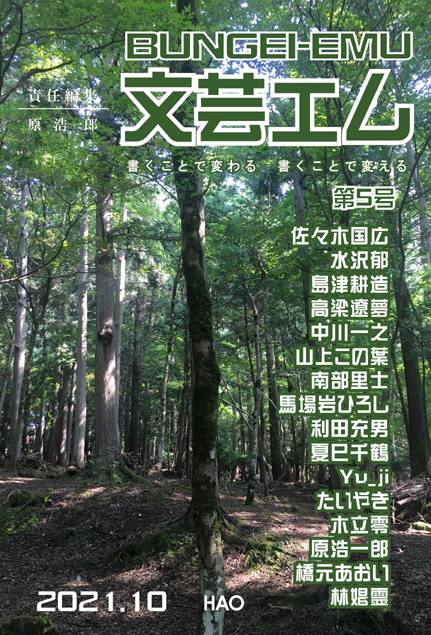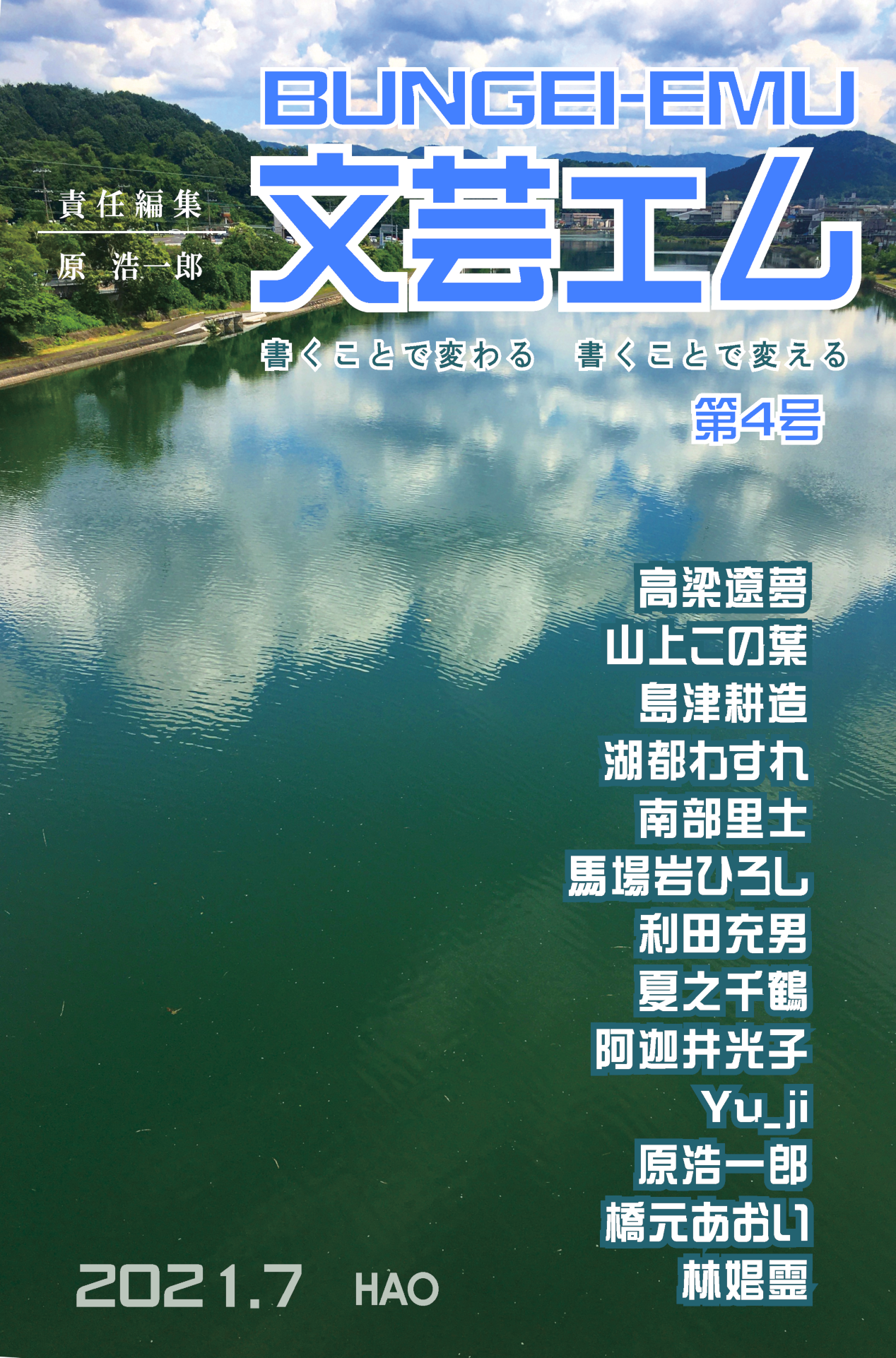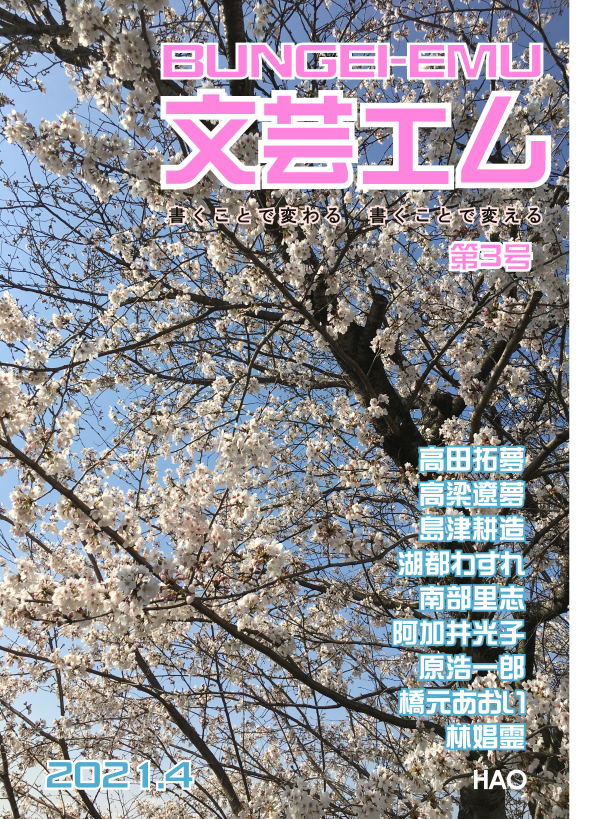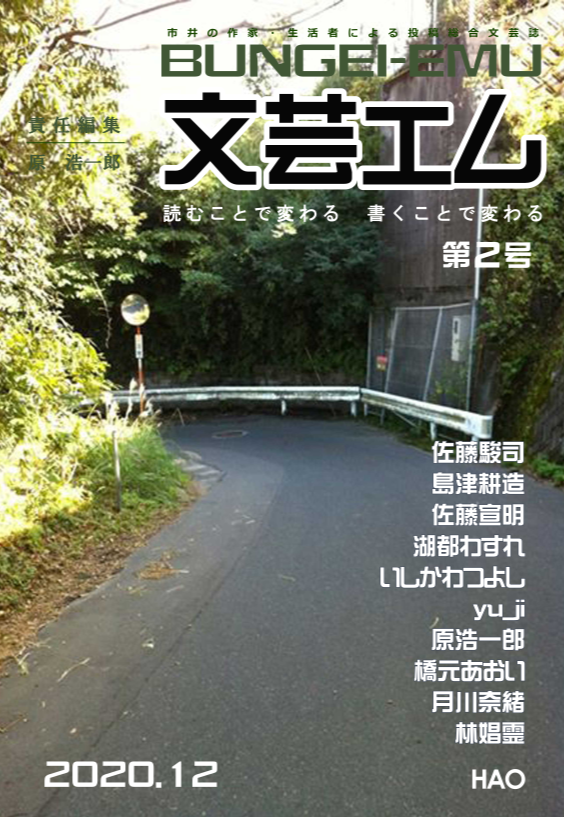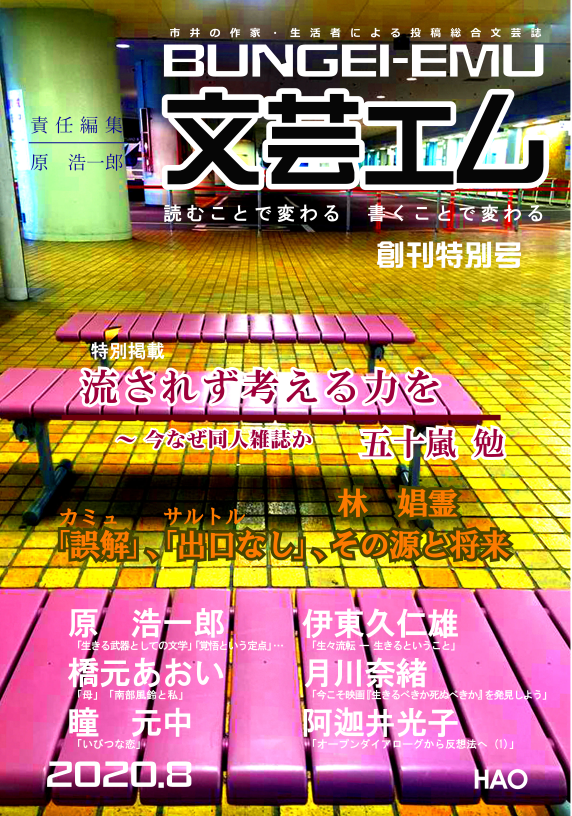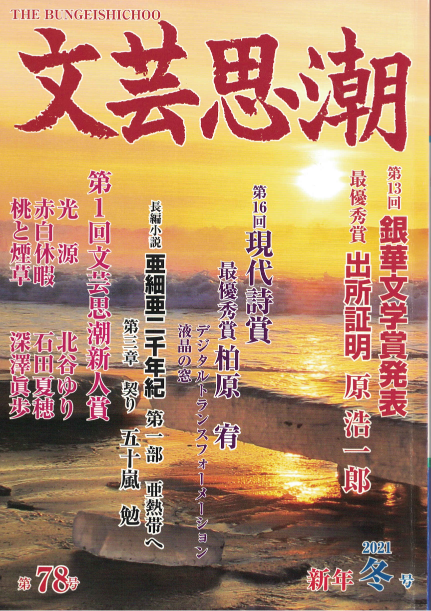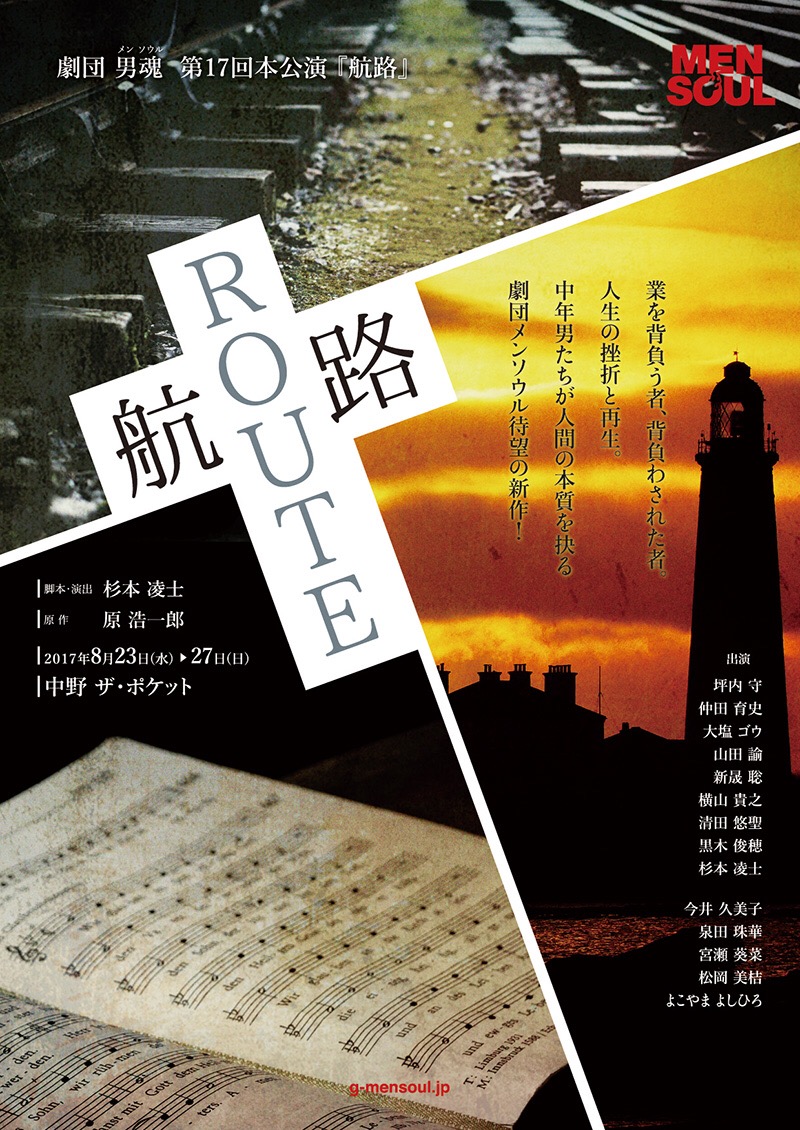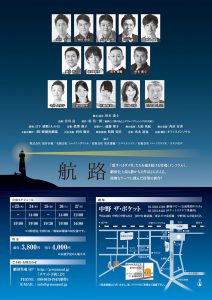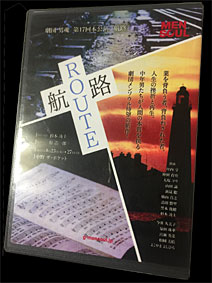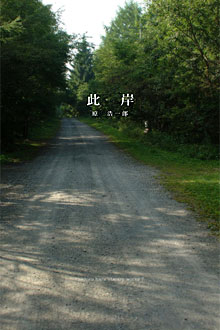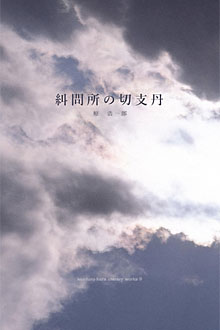浅田彰氏による西洋哲学史連続講座1「古代ギリシャから考える」(2025.5.10 NHK文化センター京都)
昨年の熊野大学で初めて浅田彰氏の講演を聞いた。後に「新潮」で特集された記事のレポートでは触れられていなかったが、参加者に向かって挑み煽るように「男であるということが恥ずかしくないのか」という意味の言葉が二度にわたって強い口調で発せられた。深く印象に刻まれている。動画で80年代当時のものから、最近の講演まで視聴してはいたが、やはり生で聞く言葉は格別に響いた。
古書で柄谷行人と共同編集の「批評空間」などを特に関心あるテーマの特集号を選び購入したことはあったが、まったく太刀打ちができなかった。素養が欠けているだけでなく、自分の知能の低さを突きつけられる。そもそも「構造と力」もあらためて数年前に図書館で借りたが、やはり理解できなかった。
市民向け講座ではあっても「浅田彰」が講師であれば、研究者も受講するだろうからレベルについていけるだろうかと不安はあった。自明の了解事項としてスピノザだのフッサールだのを引き合いして語り出されてももうお手上げである。しかし心配は無用であった。
連続6回隔週講義の初回、テーマは「古代ギリシャから考える」。講義内容には詳細触れない。
最高だった。ところどころで少し小声になって素早く毒舌風の放言をもらしながら、ビシバシと入門編風の説話を早口で頻回ワープしながらコラージュ風に重ね語られてゆく。話芸と言えば失礼か。「つまり私が言いたいのは」と区切りつつ、一旦聴衆を振り返ってはまた先へ急ぐそのリズムが心地よいのだ。私としては当然ながら哲学と文学のつながりにグッと関心が惹きつけられるのだが、「オイデュプス王」のくだりで「文学に潜在する実存の哲学」と強調された部分の、氏の言う「実存」の哲学とは?と引っかかって意識された。それは、いまだもって理解がしっかり及ばないソクラテスの「悪法も法なり」についても「ブリリアントな敗北」と紹介されたことにもかかわる、いかに生きるべきか、そして、いかに死ぬべきか?という問いに重なるのだろうか。もう一度講義の配信を視聴して確かめたい。
ちょうど数日前にヒアリングボイスの佐藤和喜雄さんと日臨心共同代表の栗原毅さんと3人で「『心理治療を問う』を読む」連続オンラインシンポの打ち合わせをしていた際に、「日本軍の毒ガス展」をめぐって「問い」をあらためて大切にするあり方を語り合っていたため、いっそう想いを深めることとなった。
また個人的には前日に友人から癌闘病の話を聞いたことがずっと心にあったのは当然のことで、生きようと死にようの問いに心が杭打たれていたことにも響いたのだと思う。
とまれ、次回の講義は翌々週である。ちょうど「WORKS2」の原稿締切の日だ。おそらく嫌な現実から逃避する熱量を以てきっと熱心に受講していることだろう。楽しみだ。